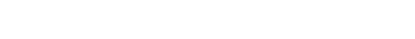<TOPICS>厚生労働省も注目するワークエンゲージメントとは!?
ワークエンゲージメントを高める方法とは?オフィス環境がワークエンゲージメントに与える影響を解説!

ワークエンゲージメントとは

ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対してポジティブな感情を持ち、充実している状態を指します。
このポジティブな感情は、特定の出来事や行動に向けられた一時的なものではなく、仕事全般に向けられた持続的かつ安定的な状態として特徴づけられます。近年、労働者の仕事のパフォーマンスの向上に大きく関わることから、企業経営において重要な指標として注目を集めています。
オランダのユトレヒト大学のウィルマー・B・シャウフェリ教授によると、ワークエンゲージメントは以下の3つの要素が整った状態として定義されています。
- 1.活力:仕事に取り組む際の高いエネルギーと心理的な回復力を持ち、困難な状況でも粘り強く取り組める状態
- 2.熱意:仕事に誇りややりがいを感じ、新しい商品開発やサービスを生み出そうと積極的に取り組める状態
- 3.没頭:仕事に取り組んでいる際に幸福感を感じ、時間が早く進むような感覚を得られている状態
参照元:厚生労働省「第3章 「働きがい」をもって働くことのできる環境の実現に向けて」、一般社団法人日本職業・災害医学会「ワーク・エンゲイジメントに注目した個人と組織の活性化」
- ワークエンゲージメント類似用語の違い-
ワークエンゲージメントと似た概念として、ワーカホリズム、バーンアウト(燃え尽き)、職務満足感があります。これらの用語はそれぞれ異なる特徴を持っています。
ワーカホリズム(ワーカホリック)は、仕事への活動水準は高い状態を保っているものの、仕事に対して否定的な状態を指します。多くの場合、「仕事を失うことへの不安から仕事をしなければならない」という心理状態に陥っている状況です。
バーンアウト(燃え尽き症候群)は、ワークエンゲージメントとは対極に位置する概念です。仕事や会社に対する不満や疲労感から、ネガティブな感情に陥り、社会的活動を停止し、意欲を喪失してしまう状態を表します。
職務満足感は、仕事を評価した結果として生じるポジティブな状態を指します。ワークエンゲージメントが仕事をしている時の感情や認知を指すのに対し、職務満足感は仕事そのものに対する感情や認知を示す点で異なります。また、仕事に没頭している状態とは異なり、活動水準が低い場合も含みます。
厚生労働省も注目するワークエンゲージメントの重要性

2019年9月、厚生労働省は「令和元年版労働経済の分析(労働経済白書)」においてワークエンゲージメントを特集し、その重要性を強調しました。この背景には、深刻化する労働人口の減少と人材の流動化という課題があります。副業の解禁や転職市場の活性化、テレワークの導入等による働き方の多様化により、企業が労働者との継続的な関係を維持することが難しくなってきているのです。
さらに、「人的資本経営」という考え方の浸透も、ワークエンゲージメントへの注目を高める要因となっています。人的資本経営とは、人材を単なるコストではなく、価値を生み出す資本として捉え、投資対象として経営を行う考え方です。経済産業省の「人材版伊藤レポート」では、人的資本経営に必要な要素として、従業員が主体的、意欲的に取り組める状態(従業員エンゲージメント)が重要視されています。
一方で、国際比較調査によると、日本のワークエンゲージメントは他国と比較して相対的に低い水準にあることが明らかになっています。この結果については慎重な解釈が必要とされているものの、日本人がポジティブな感情や態度の表出を抑制する傾向があることが一因として指摘されています。集団の調和を重視する日本の文化的背景により、仕事への「活力」「熱意」「没頭」が内在していても、それを表現することを控えめにする傾向があるのです。
このような状況を踏まえ、企業は単に人材を揃えるだけでなく、従業員が主体的に仕事に取り組めるよう、ワークエンゲージメント向上を意識した施策を行うことが一層重要となっています。
ワークエンゲージメントを高めるメリット

ワークエンゲージメントの向上は、企業に様々なメリットをもたらします。
具体的には以下の5つの効果が期待できます。
- ・従業員のモチベーション・パフォーマンスの向上
- ・定着率の向上
- ・生産性の向上
- ・顧客満足度の向上
- ・メンタルヘルスの向上
以降では、それぞれについて解説します。
- 従業員のモチベーション・パフォーマンスの向上-
ワークエンゲージメントが向上すると、従業員の仕事に関する学習意欲が高まり、「最新の技術を取得したい」「経営技術を磨きたい」「語学力を伸ばしたい」といった具体的な行動につながり、自己啓発の機会も増加します。
このような意欲的な姿勢は、より質の高い業務遂行を可能にし、通常の職務以外の業務にも前向きに取り組む姿勢を育みます。
- 定着率の向上-
従業員のワークエンゲージメントを高めることで、離職の意思が低下することが明らかになっています。厚生労働省の調査でも、新入社員の入社3年後の定着率や従業員の離職率は、ワークエンゲージメントスコアと相関関係があることが示されています。これにより、採用に関するコストを抑制することができ、中長期的な人材育成施策の実現が可能となります。
- 生産性の向上-
厚生労働省の調査によると、「生産性が向上した」と実感している従業員ほど、ワークエンゲージメントスコアが高いことが明らかになっています。
学習した知識や経験は業務の質を向上させ、役割行動やそれ以外の業務にも前向きに取り組むようになることで、組織全体の生産性向上につながります。
参照元:ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について
- 顧客満足度の向上-
ワークエンゲージメントの高い従業員の姿は、顧客に信頼や安心感を与えます。例えば営業職の場合、自社の製品に自信を持ち、やりがいを感じながら働く従業員は、顧客に対してより良い印象を与えることができます。また、商品開発においても、ワークエンゲージメントが高い従業員のほうが良質な商品を生み出しやすいという結果が出ています。
- メンタルヘルスの向上-
ワークエンゲージメントが高い従業員は、業務における苦痛が少なく、私生活でもストレスを感じにくいことが分かっています。近年、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者や退職する労働者が増加傾向にある中、ワークエンゲージメントの向上は、睡眠の質や疲労感など従業員の健康状態の改善に貢献します。
企業にとって従業員のメンタルヘルスケアは重要な課題となっており、メンタルヘルスチェックと併せてワークエンゲージメント向上施策に取り組むことで、より効果的な成果が期待できます。
参照元:厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況」
ワークエンゲージメント向上に必要な2つの要素

ワークエンゲージメントを高めるためには、組織として適切な環境や資源を提供することが重要です。具体的には以下の2つの要素が必要とされています。
【ワークエンゲージメント向上に必要な2つの要素】
- ・個人の資源
- ・仕事の資源
これらの2つの要素は密接に関係しており、効果的なワークエンゲージメント向上を実現するためには、両者をバランスよく充実させることが求められます。
- 個人の資源-
個人の資源とは、心理的なストレスを軽減しモチベーションをアップするための、働く人個人が持つ内的要因を示します。具体的には、「自己効力感」「自尊心」「ポジティブ思考」などが個人の資源として挙げられます。
特に重要な要素が「自己効力感」です。自己効力感とは、乗り越えなければならない問題が起こったときに自分なら乗り越えられると認識できることを指します。自己効力感が高い状態では「自分ならこの仕事を成し遂げることができる」という確信を持って業務に取り組むことができます。個人の資源の中でもワークエンゲージメントの高さと相関関係にあり、ワークエンゲージメントが高い人ほど自己効力感も高い状態にあることが分かっています。
- 仕事の資源-
仕事の資源とは、仕事の効率化を測り、仕事を通じた成長実感を得られるようにすることを通じて、仕事へのモチベーションを高めることを指します。具体的には、上司のサポートや、仕事に対する裁量権の付与、適切なフィードバック、ミッションの多様性などが含まれます。
仕事の資源を高めるためには、個人ではなく組織・チームとして能力や経験を最大限に発揮して取り組む「チームビルディング」が重要になります。仕事の資源はワークエンゲージメントと相関関係にあり、仕事の資源を高めていくことで、企業に対しての信頼や仕事への意欲が向上します。また、仕事の資源が充実することで個人の資源も充実するという好循環を生み出すことが可能です。
オフィス環境がワークエンゲージメントに与える影響

従業員の個人の資源と仕事の資源を充実させるためには、教育制度の整備や組織風土の改革、社内コミュニケーションの活性化など、包括的なアプローチが必要です。その中でも、オフィス環境の整備は重要な要素の一つとなっています。
世界の主要国を対象とした調査によると、オフィスに対する満足度とワークエンゲージメントには明確な相関関係が確認されています。特に、心理的安全性を確保できるオフィス環境は、ワークエンゲージメントの向上に大きく寄与することが明らかになっています。
しかしながら、日本のオフィス環境の現状には課題があります。調査によると、日本では集中しづらいオープンな執務スペースで働く従業員の割合が78%と、グローバル平均の23%と比較して突出して高くなっています。さらに、オフィス以外の場所で仕事をする機会が「まったくない」という回答が94%(グローバル平均55%)となっており、働く場所の選択肢が極めて限られていることが分かります。このような環境は、従業員の個々のパフォーマンスに直接影響を及ぼし、ワークエンゲージメントの低下にもつながっているのです。
こうした課題に対応するため、近年では多様な働き方に対応したオフィス環境の整備が進んでいます。例えば、集中して仕事に没頭できる個室ブースや、リラックスして思考を深められるソファスペース、知的刺激を得られる図書スペース、リフレッシュできるカフェスペースなどの導入が増えています。また、従業員同士のコミュニケーションを促進するためのオープンなミーティングスペースや、顧客との打ち合わせに適した商談コーナーなども、心地よい職場環境を作り出す重要な要素となっています。
このように、従業員の多様なワークスタイルに対応し、心理的安全性も確保されたオフィス環境を整備することは、ワークエンゲージメントの向上に大きく貢献するのです。
参考元:産業・組織心理学研究 2021 年,第 34 巻,第 2 号,179-193
「オフィスにおける働く場所の選択肢とワークエンゲージメントの関係: 心理的安全性の知覚による媒介効果の検討 」、「世界のエンゲージメントと職場環境実態」日本スチールケース株式会社
ワークエンゲージメントが向上するオフィス事例
ワークエンゲージメントの向上には、従業員の多様な働き方に対応し、心理的安全性も確保されたオフィス環境が重要です。
ここでは、そうした要素を取り入れた実際のオフィス改修事例をご紹介します。
- HF浜松町ビルディング様-

HF浜松町ビルディング様の事例では、従業員の多様な働き方に対応できる柔軟なオフィス環境を実現しています。エレベーターを降りてすぐの場所に印象的なデザインを配置し、社内外問わず再び訪れたくなるような魅力的な空間を演出しています。
オフィス内には、中央の造作カウンターやファミレスブース、小上がりスペースなど、シーンに応じて使い分けができる多様なスポットを設置。さらに、集中作業や電話利用が可能な個室ブースも用意され、業務の内容に応じて柔軟に働く場所を選択できます。特に、ミーティングルームはガラスで区切ることで開放感を確保しながらも、プライバシーにも配慮した設計となっています。
関連記事:HF浜松町ビルディング セットアップオフィス 新設
- NC建材株式会社様-

NC建材株式会社様では、働きたくなる"魅せるオフィス"をコンセプトに、企業の魅力を伝えられる空間づくりを実現しています。エントランス正面には企業ロゴをプロジェクションマッピングで印象的に表現し、来客エリアと執務エリアの間にはガラスとルーバーを使用することで、視線を適度に遮りながらも開放感のある空間を創出しています。
執務室は明るいカラーをゾーン毎に配置し、チェアカラーも統一することで活気のある雰囲気を演出。また、オープンスペースには大型モニター付きの造作棚を設置し、企業情報や商材情報を共有できる場を設けることで、自然なコミュニケーションを促進しています。さらに、カフェブースはスライディングウォールで大人数の会議室としても利用可能とするなど、柔軟な働き方をサポートしています。
関連記事:NC建材株式会社様 オフィス営業所新設
- タカラスタンダード株式会社様-

タカラスタンダード株式会社様の鞍手工場では、ABW(Activity Based Working)を取り入れ、「決められた場所に囚われない」をテーマにした斬新なオフィス改修を実現しています。従来のオフィスの固定概念にとらわれず、その時々の仕事内容に合わせて最適な場所を選択できる柔軟な空間設計が特徴です。
執務エリアには、10名用のビッグテーブルを配置し、活発なコミュニケーションを促進。一方で、集中力を必要とする作業のために、仕切りを設けた集中エリアも用意されています。照明もエリアごとに工夫され、執務エリアはスポットライトでカフェのような活気ある雰囲気を、集中エリアはダウンライトで落ち着いた空間を演出しています。
さらに、床や什器には木目調の素材を多用し、ナチュラルでリラックスできる環境を実現。このように、業務内容に応じて働く場所を自由に選択できる環境づくりにより、メリハリのある働き方をサポートしています。
関連記事:タカラスタンダード株式会社様 鞍手工場 オフィス改修
- 株式会社文昌堂様-

株式会社文昌堂様のオフィス改修では、「Paper links history」という基本理念を反映させながら、従来の風通しの良い企業風土を活かした空間づくりを実現しています。特徴的なのは、7階と8階で異なる役割を持たせた設計です。7階はABW(Activity Based Working)を取り入れたコミュニケーション促進エリアとし、8階をメイン業務を行う執務エリアとすることで、業務内容や目的に応じて柔軟に働ける環境を提供しています。
7階には、マグネットウォールや商材サンプル展示スペースを設け、自然なコミュニケーションのきっかけを創出。また、可動什器を採用したコラボレーションエリアや、一人で集中できるハイカウンター席など、多様な働き方に対応できる空間構成となっています。このように、従業員の満足度向上につながる工夫が随所に施されています。
関連記事:株式会社文昌堂 様 オフィス改修
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
企業の持続的な成長には、従業員のワークエンゲージメントの向上が不可欠です。人材の流動化が進む現代において、従業員の仕事への意欲や満足度を高め、維持することは重要な経営課題となっています。オフィス環境の改善を通じてワークエンゲージメントを向上させることで、生産性の向上や離職率の低下、さらには顧客満足度の向上まで期待できます。多様な働き方に対応し、心理的安全性も確保された柔軟なオフィス環境を整備することで、従業員一人ひとりが活き活きと働ける組織を実現することができるでしょう。
TOPPANでは社会の変化や従業員のニーズの多様化に対応した、オフィスレイアウトのご提案が可能です。
様々なワークスタイル変革に対応したオフィスをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください!
関連コラム
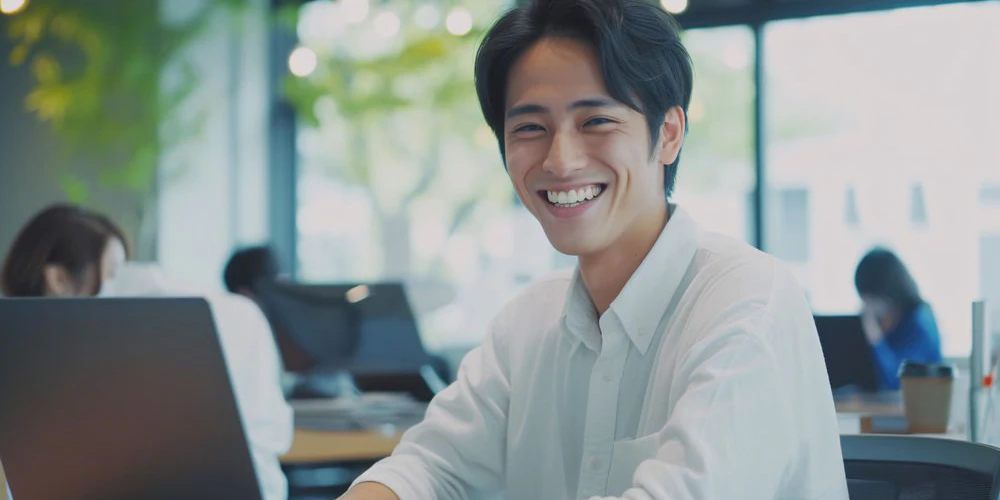
<TOPICS>労働環境とは?日本の労働問題の現状や改善策・取り組み事例を解説