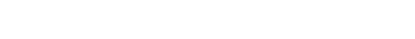<TOPICS>押さえておきたい重要なステップを解説!
出社率とは?計算方法や企業のオフィス出社率の推移・上げるポイントを解説

出社率とは

出社率とは、リモートワーク(テレワーク)を導入している企業において、オフィスに物理的に出社した従業員の割合を指します。つまり、全従業員数のうち、オフィスで勤務している従業員の人数の割合が出社率となります。
近年、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に多くの企業でリモートワークが導入されました。オフィスに出社する人とリモートワークをする人に分かれたことで、オフィスの広さやデスクの数が適切かどうかを把握するために、出社率の計算が必要になってきています。
出社率を把握することで、オフィススペースの必要性を正確に判断できます。たとえば出社率が低い場合は、オフィススペースを縮小してコストを削減できる可能性があります。逆に出社率が高い場合は、スペースが不足していないか検討が必要です。
また出社率から、従業員の勤務状況や働き方の実態を知ることができます。出社率が低いようであれば、従業員のモチベーションや健康面に課題がある可能性も考えられるでしょう。
以上のように、出社率の計算はオフィスの最適化や従業員の働き方改善につながる重要な指標と言えます。テレワーク導入企業においては、出社率の把握と管理が欠かせません。
出社率計算の目的

企業が出社率を計算する主な目的は、次の2点です。
- ・勤務状況の把握
- ・オフィススペースの最適化
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
- 勤務状況の把握 -
出社率を計算することで、企業は従業員の勤務状況や出勤パターンを把握できます。例えば出社率が低い場合、従業員のモチベーションが下がっていたり、体調管理に問題があったりする可能性があります。逆に計画的な出社とテレワークの併用ができていれば、柔軟な働き方が実現できている証拠とも言えるでしょう。
勤務状況を可視化することで、企業は従業員一人ひとりに適した働き方の提案や、組織全体の生産性向上につなげられます。社員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の定着にもつながる効果が期待できるのです。
- オフィススペースの最適化 -
コロナ禍でテレワークが普及したことを契機に、多くの企業でオフィスの見直しが進んでいます。出社率を正確に把握することは、無駄のないオフィス設計に役立ちます。
例えば出社率が平均20%程度であれば、フロアの集約などでオフィス面積を縮小し、賃料などのコストを削減できるかもしれません。一方で出社率が高めで、固定席の確保が難しくなっているようであれば、オフィスの拡張を検討する必要があります。
出社率から導き出したオフィスの利用実態を基に、フリーアドレスの導入やサテライトオフィスの設置など、働き方に合った柔軟なオフィス環境を整備できます。ムダのない最適なオフィス運営は、コスト削減だけでなく従業員の働きやすさにもつながるのです。
以上のように、出社率の計算は勤務状況の可視化とオフィス環境の最適化の両面から、企業経営に大きなメリットをもたらします。継続的な出社率の把握と分析は、ニューノーマル時代のオフィス戦略に欠かせないと言えるでしょう。
出社率の計算方法

出社率は、以下の計算式で求められます。
【計算式】
出社率=出社日数÷総可能出社日数×100
この計算式の意味を解説しますと、「ある期間(例:1週間、1ヶ月)に実際にオフィスに出社した日数」を「その期間中に出社可能だった日数(営業日数)」で割り、100を掛けることで出社率が算出されます。
出社率を正確に計算するためには、以下のステップを踏む必要があります。
- 1.計算対象期間の設定:出社率を求める期間(週、月、年など)を決定する。
- 2.出社日数の集計:対象期間内で、各従業員がオフィスに実際に出社した日数を集計します。テレワークの日は含みません。
- 3.総出社可能日数の算出:対象期間内の営業日数(週5日、月20日など)から、休暇等で出社できない日数を除いた日数を総出社可能日数とします。
- 4.計算式への当てはめ:集計した出社日数と総出社可能日数を計算式に代入し、出社率を算出します。
出社率の計算には、以下の点に注意が必要です。
- 出社日数には、オフィスで勤務した日のみを含め、テレワークやリモートワークの日は含めないこと。
- 総出社可能日数は、会社の営業日・就業日ベースで計算し、従業員個人の休暇等は控除すること。
- 時短勤務やフレックス制度等で、出社時間が一定でない場合の取り扱いをルール化しておくこと。
以上が出社率の基本的な計算方法です。日々の出社状況を正確に記録し、適切に集計・算出することが肝要となります。出社率の定点観測により、オフィスの効率的運用や従業員の働き方改善に役立てていきましょう。
企業のオフィス出社率は増加傾向

ザイマックスグループのザイマックス不動産総合研究所が2023年春に実施した「大都市圏オフィス需要調査2023春」によると、企業の平均出社率は70.7%となっています。この数値は、2020年秋以降20%前後で推移していた「完全出社」の割合が25.7%まで増加したことを示しており、コロナ禍以降で最も高い水準です。
オフィス出社率が増加傾向にある背景には、以下のような理由が考えられます。
【コミュニケーションの活性化】
テレワークの長期化で、対面コミュニケーションの重要性が再認識されつつあります。特に新入社員の教育やチームビルディングには、オフィスでの直接的な交流が欠かせません。
【業務効率の向上】
オフィスでの協働作業やフェイスtoフェイスの議論は、創造性を刺激し、生産性を高める効果があります。プロジェクトの進捗管理などには、出社を伴う業務の方が適しているケースも多いでしょう。
【働き方の最適化】
完全テレワークの課題が明らかになる中、オフィス勤務とテレワークのベストバランスを模索する動きが広がっています。適度な出社は、メリハリのある働き方の実現につながります。
ザイマックス不動産総合研究所の調査からは、オフィス出社とテレワークのハイブリッド型勤務が主流になりつつある実態が浮き彫りになりました。働き方改革も謳われる昨今、改めてオフィスの価値や出社の意義が問い直されている状況と言えるでしょう。
各企業においては、自社の業務特性や組織風土に合わせて、出社とテレワークの最適な組み合わせを模索していくことが求められます。出社率の適切なコントロールを通じ、ニューノーマル時代のオフィス活用法を確立していくことが肝要と考えられます。
企業にとって出社率は上げるべきか

出社率を上げるべきか、それとも下げるべきかは、一概には言えません。企業の業種や規模、業務内容、組織風土などによって、最適な出社率は異なるからです。
例えばIT企業など、個人の集中力を必要とする仕事が多い業界では、テレワークの導入によって生産性が上がるケースが多く見られます。一方で製造業など、現場での作業が不可欠な業種では、出社率の低下が業績に直結しかねません。
従業員間のコミュニケーションや協働作業の重要性も、出社率を考える上で無視できません。アイデア出しや問題解決など、対面での議論が欠かせない職種もあれば、オンラインツールを活用すれば十分な成果が得られる職種もあるでしょう。
こうした点を踏まえると、以下のような企業は出社率を上げることを検討すべきと言えます。
【対面での顧客対応が必要な企業】
営業職など、顧客との直接的なコミュニケーションが業績を左右する企業では、出社率の向上が求められます。信頼関係の構築には、何にも代えがたい対面での交流が欠かせないからです。
【チームワークやコラボレーションが重視される企業】
新製品の開発や複雑なプロジェクトの遂行など、部門横断的な協力が不可欠な企業では、出社率を上げることでシナジー効果を高められます。立場の異なる社員が一堂に会することで、斬新なアイデアが生まれやすくなるのです。
【社員教育や人材育成に力を入れる企業】
新入社員の指導やOJTなど、先輩社員からの直接的な教えが重要な企業では、出社率の引き上げが欠かせません。仕事の進め方やコツなどは、オフィスでの何気ない会話や、先輩の行動を見て学ぶことも多いのです。
【組織一体感や帰属意識を大切にする企業】
社員の一体感醸成や企業文化の浸透を重んじる企業では、出社率を高めることで組織力の強化につなげられます。朝礼や社内イベントなどを通じて、社員間の絆を深めることができるからです。
以上のように、出社率の最適化は企業の特性に応じて判断すべき経営課題と言えます。自社の強みを活かし、業績向上につなげるための出社率のコントロールが求められるのです。
もちろん、オフィス出社とテレワークのベストミックスを探ることも重要です。働き方改革が叫ばれる中、多様な勤務形態を選択肢として用意することが、優秀な人材の獲得・定着につながるでしょう。
出社率を上げるためのポイント

企業が出社率を上げるためには、以下の2点がポイントになります。
- ・オフィスで働く価値を認識してもらう
- ・出社したくなるオフィススペースを作る
まず、オフィスで働くことの価値を従業員に再認識してもらうことが重要です。テレワークの普及で、必ずしもオフィスに来なくても仕事ができることが明らかになった今、改めてオフィスの存在意義を問い直す必要があるのです。
例えば、対面でのコミュニケーションがもたらすメリットを強調することが有効でしょう。オンラインでは伝わりにくい微妙なニュアンスや、雑談から生まれるアイデアなど、オフィスならではの価値をアピールすることで、出社の動機づけにつなげられます。
加えて、部署横断的なプロジェクトや社内イベントなど、オフィスで協働する機会を意図的に設けることも効果的です。共に汗を流し、同じ目標に向かって努力する経験は、出社の意義を実感させてくれるはずです。
次に、従業員が「行きたい」「働きたい」と思えるオフィス環境の整備が欠かせません。出社率を上げるには、オフィスの魅力を高めることが何より重要だからです。
快適で機能的なワークスペースの提供はもちろん、リラックスできるラウンジやカフェスペースの設置も検討しましょう。仕事の合間に息抜きできる環境があれば、オフィスに足を運ぶ楽しみが生まれます。
さらに、フリーアドレスやコワーキングスペースの導入など、柔軟な働き方を支援する施策も有効です。自分に合ったスタイルで仕事ができる選択肢があれば、出社への抵抗感も和らぐでしょう。加えて、社員の健康やウェルビーイングに配慮した設備投資も重要です。エルゴノミクスに基づいたデスクやチェア、アメニティの充実など、心身の負担を軽減する工夫が求められます。
「行きたくなるオフィス」づくりは、出社率アップの鍵を握ります。従業員目線に立った環境整備を進めることで、自然と出社率の向上につなげていくことが可能なのです。
出社率向上が期待できるオフィス事例
実際に、どのようなオフィス環境づくりが出社率向上につながるのでしょうか。
ここでは、オフィス改修をおこなった3社の事例から、具体的なポイントを学んでいきましょう。
- 株式会社文昌堂様 -

文昌堂様は、オフィス改修にあたり「自社の魅力をアピールできる」「部門間連携を高める」ことを目指されました。7階はコミュニケーションを促進するエリア、8階はメイン業務の執務エリアと、階層ごとに役割を持たせたのがポイントです。
7階のコミュニティエリアには、商材サンプルや掲示物を展示できるマグネットウォールとキャビネットを設置。社内外への情報発信とコミュニケーションのきっかけづくりを両立しています。
コラボレーションエリアは、利用人数や目的に合わせて自由にレイアウトを変更できる、フレキシブルな設計が特徴。カラフルな家具が創造性を刺激し、カジュアルな雰囲気が対話を促します。
オフィスの歴史と文化を残しつつ、これからの感性も取り入れた文昌堂様の改修事例からは、「伝統と革新の融合」「コミュニケーションを生むしかけ」がキーワードとして浮かび上がります。
関連記事:株式会社文昌堂 様 オフィス改修
- 株式会社ロッテ様 -

ロッテ様は執務室の改修を通じて、フレキシブルな働き方の実現を目指されました。多様なワークエリアと、自由にレイアウトを変更できる共用エリアの増設がポイントです。
オープンで遮蔽物の少ない設計は、偶発的なコミュニケーションを生み出す効果があります。加えてロッテ様らしさを表現するため、ブランドカラーを差し色として使用するなど、企業アイデンティティーにも配慮しています。
自社製品を陳列できるディスプレイ棚の新設も、企業風土醸成の有効な手段と言えるでしょう。
ロッテ様の事例からは、「柔軟性の高い共用スペース」「ブランドイメージの体現」「社員の一体感醸成」といった、出社率向上のヒントが得られます。
関連記事:株式会社ロッテ様 執務室改修
- NC建材株式会社様 -

NC建材様は、オフィス営業所の新設にあたり、多様な業務スタイルに対応しつつ、「働きたくなる魅せるオフィス」を目指されました。
エントランス正面の企業ロゴにはプロジェクションマッピングを設え、来訪者に強い印象を与えます。ガラスとルーバーの組み合わせで、エントランスからもオフィス内の活気が伝わる設計も特徴的です。
ゾーンごとに明るいカラーを配したオープンな執務エリアは、コミュニケーションと生産性の向上に寄与。モニター付きの造作棚は、情報共有とディスカッションを促進します。
気軽な打ち合わせに適した個別ブースや、静かに集中できるカフェブースの設置で、シーンに合わせた最適な働き方を後押ししています。しているのも見逃せません。
NC建材様の事例が示唆するのは、「オフィスの顔づくり」「場に応じた空間設計」「ワークスタイルの多様化」です。
3社の事例に共通するのは、「コミュニケーションの活性化」「企業文化の体現」「働き方の柔軟性」を重視する点です。出社したくなるオフィス作りには、これらの要素を自社の特性に合わせて織り交ぜていくことが肝要と言えそうです。
関連記事:NC建材株式会社様 オフィス営業所新設
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
本記事では、ニューノーマル時代に重要性を増す出社率について、その定義から計算方法、最新の動向まで網羅的に解説しました。出社率を適切に管理することは、従業員の勤務状況の把握とオフィス環境の最適化につながり、生産性向上と企業価値の向上に寄与します。自社の特性に合わせて出社率をコントロールし、コミュニケーションの活性化、企業文化の体現、働き方の柔軟性を実現するオフィス作りに取り組むことが、ニューノーマル時代を勝ち抜くカギとなるでしょう。
TOPPANでは、調査・企画~設計・施工まで一気通貫で空間づくりをサポートいたします。
オフィスのレイアウト・内装デザインはもちろんのこと、拠点の構想・企画に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
関連コラム

<TOPICS>オフィスコミュニケーションを活性化するには?レイアウトのコツや事例を紹介

<TOPICS>オフィスデザインのコンセプトとは|決め方やポイント、成功事例を紹介