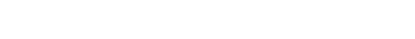<TOPICS>生産性向上との違いは?効率化を進める具体的な手順もご紹介
業務効率化のアイデア11選!具体例や進め方のポイントを徹底解説

業務効率化とは

企業の生産性向上とコスト削減に直結する重要な課題として、業務効率化への取り組みが注目を集めています。特に近年は、テレワークの導入や働き方改革の推進に伴い、より効率的な業務運営が求められています。
本質的な業務効率化とは、業務プロセスから「ムリ」「ムダ」「ムラ」を見出し、それらを排除することで、限られたリソースを最大限に活用することを指します。
- 生産性向上との違い -
業務効率化と生産性向上は、しばしば混同されがちな概念です。以下の表で、それぞれの特徴を示します。
項目 | 業務効率化 | 生産性向上 |
|---|---|---|
目的 | リソース投下量の削減 | より少ないリソースで高い成果を出す |
焦点 | ムリ・ムダ・ムラの排除 | アウトプットの最大化 |
手法 | 既存業務の改善 | 新たな価値創造 |
生産性向上は既存のリソースからより大きな価値を生み出すことを目指す一方、業務効率化は同じ成果を上げるために必要なリソースを最小化することに重点を置いています。業務効率化は生産性向上を実現するための重要な施策の一つとして位置づけられます。
- 効率化で得られるメリット -
業務効率化を実現することで、企業は以下のメリットを享受できます。
- ・時間的コストの削減効果
- ・従業員のモチベーション向上効果
- ・企業利益の増大効果
時間的コストの削減効果として、無駄な作業プロセスを省くことで、残業時間の削減が可能になります。これにより、人件費の抑制だけでなく、従業員の身体的負担も軽減されます。
従業員のモチベーション向上効果については、労働時間の短縮と働きやすい環境の実現により、従業員満足度が向上します。これは社員の定着率向上にも寄与し、「働き方改革」の実現に向けた重要な要素となっています。
企業利益の増大効果に関しては、業務の生産性向上により、社員が新たな取り組みやチャレンジに時間を割くことが可能になります。これにより、企業の成長機会が拡大し、結果として収益性の向上につながります。
- 効率化しやすい業務 -
業務効率化を進める上で、特に効果が高い業務には主に3つの特徴があります。
- ・繰り返しが多い
- ・標準化しやすい
- ・自動化しやすい
繰り返しが多い業務の代表例として、データ入力やフォーム処理が挙げられます。これらの作業はRPAなどの自動化ツールを活用することで、迅速かつ正確な処理が可能になります。
標準化しやすい業務には、請求書処理や在庫管理などがあります。これらの業務は、明確なルールに基づいて実施されるため、一貫した品質を保ちながら効率化を図ることができるでしょう。
自動化しやすい業務としては、スケジューリングや電子メールの管理、レポート生成などが該当します。これらはツールを活用することで、作業時間を大幅に削減できます。
さらに、一見すると効率化が難しそうな非定型業務であっても、工夫次第で効率化は可能です。例えば、企画業務においては、過去の成功事例やノウハウをデータベース化することで、アイデア創出のプロセスを効率化できます。また、顧客対応業務では、よくある質問と回答をまとめたFAQを整備することで、対応時間の短縮が可能です。
業務効率化を実現する11のアイデア

業務効率化を実現するには、具体的な施策とその実践方法を理解することが不可欠です。以下では、すぐに導入可能な11のアイデアについて、それぞれの実施方法や期待される効果を解説します。
これらのアイデアは、単独での実施はもちろん、複数を組み合わせることでより高い効果を発揮できるでしょう。
- 無駄な業務の洗い出しと削減 -
業務の棚卸しから始めることで、効率化の糸口が見えてきます。まずは、全ての業務を時間帯や担当者、工数などの観点で詳細にリストアップします。特に日常的に実施される定型業務や、手間のかかる作業に注目しながら、抜け漏れのないように整理を進めます。
無駄な業務を判断する際の基準として、「本当にその作業が必要か」「誰のために行っているのか」「成果に繋がっているか」という3つの視点で評価します。例えば、同じデータを複数回入力する作業や、使用頻度の低い報告書の作成などは、削減を検討する対象となります。
効果測定においては、削減前後の作業時間や工数を比較することで、具体的な成果を数値化できます。さらに、従業員の業務負担感についてもヒアリングを行い、定性的な評価も加えることで、総合的な効果把握が可能となります。
- タスクの優先順位付けと最適化 -
効率的な業務推進のために、タスクの優先順位付けは重要な要素となります。以下の表は、タスクの優先度を判断する際の基準を示しています。
優先度 | 緊急性 | 重要性 | 対応方針 |
|---|---|---|---|
最優先 | 高 | 高 | 即時対応 |
高 | 低 | 高 | 計画的対応 |
中 | 高 | 低 | 委託検討 |
低 | 低 | 低 | 廃止検討 |
この優先順位に基づき、時間管理を徹底することで、重要な業務に注力できる環境が整います。例えば、時間のかかる業務は早めに着手し、短時間で終わる業務はその合間に処理するなど、効率的なタスク配分が可能となります。
特に注目すべきは上記表の2行目、「高優先度(緊急性:低、重要性:高)」の業務です。これは『7つの習慣』で説明される「第2領域」にあたり、「効果性の領域」とも呼ばれます。人材育成や新規事業企画など、すぐには結果が出なくても将来の成長に不可欠な活動が含まれます。
第2領域の活動に計画的に取り組むことで、将来的な緊急対応(第1領域)を減らし、業務の好循環を生み出せます。第3・第4領域の活動を削減して生み出した時間を第2領域に投資することが、持続的な業務効率化の鍵となります。
- RPAによる業務自動化の推進 -
RPAは繰り返し発生する定型業務の自動化に特に効果を発揮します。適した業務の選定基準として、作業手順が明確で変動が少ないこと、大量の処理が定期的に発生すること、人的ミスのリスクが高い作業であることなどが挙げられます。
導入手順としては、まず対象業務の選定と業務フローの可視化を行います。次に、ROIを計算するため、現状の工数や人件費を基にコスト試算を実施します。その後、テスト運用を経て本格導入へと進みます。
実際に導入した際の事例では、受発注業務の自動化により月間の作業時間が1,200時間削減されたケースや、入力業務の自動化で月に450時間の改善効果を実現したケースなどが報告されています。
- 標準化されたマニュアルの整備 -
効果的なマニュアルを作成するためのポイントとして、以下の3つがあります。
- ・見やすさ(レイアウト、図表活用)
- ・わかりやすさ(手順の明確化)
- ・更新のしやすさ(メンテナンス性)
まず見やすさの観点では、適切な余白やフォントサイズの設定、図表やフローチャートの効果的な活用が重要です。
次にわかりやすさについては、手順を具体的かつ簡潔に記述し、必要に応じて画像や動画を活用します。更新のしやすさについては、データをモジュール化し、部分的な修正が容易な構造にすることがポイントです。
マニュアル運用においては、定期的な見直しと更新のルールを設定することが重要です。例えば、四半期ごとの見直し時期を設定し、現場からのフィードバックを反映する仕組みを構築します。また、マニュアルの保管場所や参照方法についても、誰もが簡単にアクセスできる環境を整備します。
- 業務フローの見える化と改善 -
業務フロー図の作成は、作業の流れを可視化し、問題点を特定するための効果的なツールです。まず、業務の開始から終了までの一連の流れを時系列で整理します。各工程における作業内容、担当者、所要時間、使用するツールなどを明確に記載します。
フロー図を活用した問題点の洗い出しでは、重複している作業や、承認プロセスの複雑さ、情報の伝達経路などに着目します。特に、作業の待ち時間や、部門間での引き継ぎポイントは、効率化の余地が大きい箇所として注意深く確認します。
- データベースの構築と活用 -
データベースの構築により、情報の一元管理と共有が容易になります。結果として、データの検索時間の短縮や、重複入力の防止、情報の正確性向上などの効果が期待できます。
必要な情報の選定では、顧客データ、製品情報、業務プロセスに関するデータなど、日常的に使用する情報を優先的に登録します。管理ルールとしては、データの更新頻度、アクセス権限、バックアップ方法などを明確に定めます。
- 複数業務の一括処理化 -
一括処理に適した業務は、類似の作業が複数回発生する場合や、まとめて処理することで効率が向上する作業です。例えば、資料のチェック業務では、一度に大量の資料を確認するのではなく、適切な量に分けて処理することで、担当者の負荷を軽減できます。
具体的な手順としては、まず業務量の適切な分割方法を検討します。次に、処理のタイミングや担当者の配置を決定し、実施後は処理時間や品質の変化を測定します。
- 人員配置の最適化とスキル活用 -
人材の適切な配置は、業務効率化の要となる重要な施策です。個々の従業員が持つ能力を最大限に活かすことで、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。
以下の観点に基づいて最適化を進めていきます。
- ・スキルマップの作成方法
- ・適材適所の判断基準
- ・配置転換の進め方
スキルマップの作成から始めることで、効果的な人員配置が実現できます。各従業員の得意分野、資格、経験年数などを一覧化し、部署ごとに必要なスキルと照らし合わせます。例えば、高いコミュニケーション能力を持つ社員を営業部門に、製品知識が豊富な社員をマーケティング部門に配置するなど、適材適所の人員配置を進めます。
配置転換を実施する際は、対象者との丁寧な面談を通じて、キャリア目標や希望する業務内容を確認します。また、新しい部署での研修期間を十分に設け、スムーズな移行をサポートします。
モチベーション維持のために、定期的なフィードバック面談を実施し、新環境での課題や成長機会について話し合います。
- 作業スピードの向上施策 -
日々の業務において、作業スピードの向上は即効性のある効率化手法として注目されています。ただし、単なる速度の追求ではなく、正確性と品質を保ちながら実施することが重要です。
スピードアップのための具体的な方法として、以下が挙げられます。
- ・ショートカットキーの活用
- ・定型文の準備
- ・テンプレートの活用
業務スピードの向上は、単純な時間短縮だけでなく、品質を維持しながら実現することが重要です。ショートカットキーの活用では、頻繁に使用する操作をキーボード操作で完結できるようにします。定型文の準備については、よく使用するメールの文面や報告書のフレーズをテンプレート化し、即座に利用できる環境を整えます。
品質を維持しながらスピードを上げるためのコツとして、チェックリストの活用が効果的です。作業の要所要所でチェックポイントを設け、ミスの早期発見と修正を可能にします。また、集中力を維持するために、適切な休憩時間の確保も重要です。
- 複数アイデアの組み合わせ活用 -
効率化施策は、複数のアイデアを組み合わせることでより大きな効果を発揮します。例えば、業務マニュアルの整備とデータベースの構築を同時に進めることで、標準化された業務プロセスと情報の一元管理が実現します。また、RPAの導入と業務フローの見直しを組み合わせることで、自動化の効果を最大限に引き出すことができます。
段階的な導入を心がけ、まずは小規模な範囲でテスト運用を行い、効果を確認しながら対象範囲を広げていきます。効果測定は、作業時間の削減率や、エラー発生率の変化、従業員の満足度調査など、複数の指標を用いて総合的に評価します。
- 働きやすいオフィスレイアウトの工夫 -
効率的なオフィスレイアウトは、コミュニケーションの活性化と業務効率の向上に直結します。部署間の連携が多い組織同士を近接させることで、移動時間の削減と情報共有の円滑化を図ります。また、打ち合わせスペースや集中作業エリアを適切に配置することで、目的に応じた作業環境を提供します。
具体的な改善ポイントとして、書類や備品の保管場所を最適化し、頻繁に使用するものを手の届きやすい位置に配置します。また、自然光を取り入れやすい配置や、適切な照明設備の導入により、従業員の快適性と生産性を向上させます。
従業員の満足度向上との両立には、個人の作業スペースにおける適度なプライバシーの確保と、コミュニケーションの促進のバランスが重要です。フリーアドレスやホットデスクの導入なども、状況に応じて検討することで、柔軟な働き方を支援できます。
業務効率化の基本的な進め方

業務効率化を成功に導くためには、体系的なアプローチが欠かせません。具体的な改善施策を実行する前に、現状分析から効果測定までの5つのステップを理解し、計画的に進めることが重要です。
以下では、各ステップでの具体的な実施方法とポイントを解説します。
- ①現状業務の可視化と分析 -
効率化の第一歩は、現状を正確に把握することから始まります。まずは全ての業務内容を詳細にリストアップし、担当部署、担当者、発生頻度、必要なスキルなどの情報を整理します。業務の洗い出しには、日報やタイムカードのデータを活用し、できるだけ客観的な情報収集を心がけます。
工数の測定では、各業務にかかる時間を具体的に記録します。単発的な作業時間だけでなく、準備や後処理にかかる時間も含めて測定することで、より正確な分析が可能になります。
分析手法の選択においては、業務の性質に応じて適切な手法を選びます。例えば、業務プロセスの分析にはフローチャートを、時間配分の分析にはタイムスタディを活用するなど、目的に応じた手法を採用します。
- ②課題・問題点の明確化 -
リストアップした業務内容を基に、具体的な問題点やボトルネックを特定していきます。
以下の視点で課題を抽出します。
- ・時間的な課題
- ・コスト面の課題
- ・品質面の課題
現場の声を積極的に取り入れることで、実務レベルでの課題が明確になります。例えば、特定の時間帯に業務が集中する、手作業による入力ミスが発生するなど、具体的な問題点を洗い出します。
原因分析では、特性要因図(フィッシュボーン分析)などのツールを活用し、問題の根本原因を特定します。表面的な症状だけでなく、その背景にある本質的な課題を把握することで、効果的な改善策の立案が可能になります。
- ③改善計画の立案とスケジュール化 -
課題を明確にした後は、具体的な改善計画を立案します。
- 1. 目標設定
- 2. 実施項目の選定
- 3. スケジュール作成
目標は具体的な数値を設定し、達成度を測定可能な形にします。例えば「残業時間を30%削減する」「入力ミスを80%削減する」といった形です。
実行計画は、ガントチャートなどを用いて視覚的に管理します。各タスクの開始日、終了日、マイルストーンを明確にし、関係者全員が進捗を共有できる環境を整えます。
- ④効率化施策の実施と進捗管理 -
定めたスケジュールに従って改善策を実行します。施策実施時は、影響範囲を考慮し、段階的な導入を心がけます。特に大規模な変更を伴う場合は、小規模なテスト運用から始めることで、リスクを最小限に抑えることができます。
進捗状況は定期的なミーティングで確認し、計画からのずれがある場合は早期に対策を講じます。問題が発生した際は、その影響度を評価し、必要に応じて計画の修正や追加対策を実施します。
- ⑤効果測定と継続的な改善 -
施策の効果を定量的・定性的に測定し、その結果をもとにさらなる改善を図ります。KPIは改善目標に応じて設定し、例えば作業時間、エラー率、顧客満足度など、複数の指標を組み合わせて評価します。
測定は定期的に実施し、目標値との差異を分析します。PDCAサイクルを確実に回すため、月次や四半期での振り返りの機会を設け、必要に応じて改善策の見直しや新たな施策の追加を検討します。特に成功事例については、他部門への水平展開も視野に入れ、組織全体の効率化につなげます。
業務効率化を実現するオフィス事例
業務効率化を実現するうえで、オフィス環境の整備は重要な要素となります。最新のオフィス改修・移転事例から、効率的な働き方を支援する空間づくりのポイントを紹介します。
それぞれの企業が抱える課題に対し、どのようなアプローチで解決を図ったのか、具体的な取り組みを見ていきましょう。
- タカラスタンダード株式会社様 -



ABW(Activity Based Working)の考え方を取り入れ、従来の固定観念にとらわれない柔軟な働き方を実現したオフィス改修事例です。
仕事の内容に応じて働く場所を選択できるよう、10名用の大テーブルを備えた開放的なワークスペースと、集中作業に適した個別ブースを設置。照明もエリアごとに使い分け、メインエリアはスポットライトでカフェのような活気ある雰囲気を、集中エリアはダウンライトで落ち着いた空間を演出しています。
関連記事:タカラスタンダード株式会社様 鞍手工場 オフィス改修
- 株式会社NICHIJO様 -



従業員満足度の向上とリクルート効果を両立したオフィス移転事例です。フリーアドレス制を導入し、背の低い什器を採用することで、社員の所在確認が容易な開放的な空間を実現。窓際には眺望を活かした会議室を配置し、ガラスパーテーションで仕切ることで圧迫感を軽減。
リフレッシュエリアにはさまざまな作業スタイルに対応できるよう、ソファやハイカウンターなど多様な什器を設置しています。
関連記事:株式会社NICHIJO様 東京支社移転
- 株式会社三洋産業様 -



「2.5th place」をコンセプトに、業務効率と快適性を両立させた本社屋改修事例です。オフィス(2nd place)に心地よさ(0.5th place)を加えることで、現場作業の疲れを癒せる空間を目指しました。
木目調のカウンターとプランターボックスで温もりのある雰囲気を演出しつつ、天井のグレー塗装でモダンさを表現。2階には可動性の高い什器を採用し、多様な会議形態に対応できるフレキシブルな空間を実現しています。
関連記事:株式会社三洋産業様 本社屋改修
- 株式会社文昌堂様 -



「Paper links history」という基本理念を体現した、7階と8階に分かれたオフィス改修事例です。7階をABWに基づいたコミュニケーション促進エリアとし、8階をメイン業務を行う執務エリアとすることで、業務内容や目的に応じて柔軟な働き方を実現。
特に7階のコラボレーションエリアでは、可動什器を採用し、利用人数や会議形式に応じて自由にレイアウト変更が可能な設計となっています。
また、マグネットウォールやキャビネットを活用し、商材サンプルや掲示物の展示スペースを設けることで、コミュニケーション機会の創出を促進しています。
関連記事:株式会社文昌堂 様 オフィス改修
- 株式会社リブ・コンサルティング様 -



コロナ禍でのリモートワーク定着を踏まえ、出社する価値を創出するオフィスデザインを実現しました。1フロアに集約された広い空間を活かし、壁を極力排除した見通しの良い執務空間を構築。床の仕上げと什器の使い分けによる効果的なゾーニングを実施し、モバイルバッテリーの採用により、フレキシブルなレイアウト変更を可能にしています。
また、中央にはLEDビジョンを備えたカウンターエリアを設置し、自然な形でコミュニケーションが生まれる工夫を施しています。
まとめ
業務効率化は、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な取り組みです。単なる時間短縮やコスト削減だけでなく、従業員の満足度向上や新たな価値創造にもつながる重要な経営課題となっています。
本記事で紹介した11のアイデアと5つのステップを実践することで、無駄を省き、生産性を向上させることが可能です。また、オフィス環境の整備を含めた総合的なアプローチにより、より効果的な業務効率化を実現できるでしょう。
オフィス見学のご案内

業務効率化を推進するオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
オフィスにおけるコミュニケーションの活性化は、企業の生産性向上や離職率の低下、新しいアイデアの創出につながる重要なテーマです。
レイアウトの工夫やフリーアドレス制の導入、マグネットスペースや社内カフェの設置など、様々な施策を通じてコミュニケーションを促進することが可能です。実際の事例から学べるポイントを参考に、自社の状況に合わせたオフィス改善を行うことで、社員の満足度や業績のアップを実現できるでしょう。
働きやすく、活気あふれるオフィス環境を目指し、コミュニケーション活性化に取り組むことをおすすめします。
最後にTOPPANではコミュニケーション促進につながるオフィスレイアウトのご提案が可能です。またオフィス移転先をご検討のお客様へ、不動産仲介会社をご紹介することも可能です。
コミュニケーションを重視したオフィスレイアウトをご検討の際は、ぜひお気軽にお問合せください!
関連コラム

<TOPICS>ABW(Acitivity Based Working)とは|メリットやオフィス事例を紹介

<TOPICS>オフィス環境改善の取り組み例7選|おすすめのグッズや事例も紹介