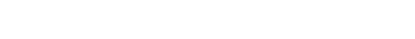<TOPICS>なぜ今コミュニケーションが重視されるのか?詳しく解説!
社内コミュニケーションの重要性とは?活性化のポイントや取り組み事例を紹介

社内コミュニケーションの重要性

社内コミュニケーションとは、企業内における社員同士の情報交換や共有、雑談など、業務内外で行われるあらゆるコミュニケーション活動を指します。具体的には、上司と部下の間での報告・連絡・相談、同僚との業務に関する情報共有、部署間での連携など、仕事を円滑に進めるために欠かせない要素となっています。
社内コミュニケーションが活性化することで、組織にはさまざまなメリットがもたらされます。適切なコミュニケーションは、社員のモチベーション向上や業務効率化による生産性アップにつながります。また、部署を超えた情報共有が促進され、組織全体の連携が強化されることで、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすい環境が整います。
従来のオフィスコミュニケーションでは、組織運営を円滑に進めることを重視し、同じ部署内での島型レイアウトが一般的でした。この環境下では、業務に関連する社員同士のコミュニケーションは取りやすいものの、他部署との交流は喫煙所や終業後の飲み会など、限られた機会に頼らざるを得ませんでした。
しかし現代では、テレワークや時短勤務など多様な働き方が広がり、従来の対面でのコミュニケーション機会が減少しています。このような変化に対応するため、フリーアドレス制の導入やカフェスペース、ミーティングスペースの設置など、部署や役職を超えた開放的なコミュニケーションを促す仕組みづくりに取り組む企業が増えています。これにより、プライベートな時間を削ることなく、業務時間内で自由なコミュニケーションが可能となっています。
社内コミュニケーションを活性化させるメリット

企業内のコミュニケーションを活性化させることで、組織にはさまざまなポジティブな効果がもたらされます。
具体的には、以下の3つの重要なメリットが期待できます。
【社内コミュニケーションを活性化させるメリット】
- ・社員のモチベーションの向上
- ・生産性の向上
- ・離職率の低下
以降では、それぞれについて解説します。
- 社員のモチベーションの向上 -
社内コミュニケーションが活発な職場では、従業員が意見や相談を発信しやすい雰囲気が生まれます。上司から叱責されたり、同僚から否定的な反応を受けたりすることへの心理的な不安が軽減され、自然と発言がしやすくなります。
こうした環境の中で、社員は働きやすさを実感し、仕事に対する意欲が高まっていきます。また、普段からコミュニケーションが活発であれば、困ったときにも速やかに周囲に相談でき、問題解決へのスムーズな対応が可能となります。
- 生産性の向上 -
円滑なコミュニケーションが実現すると、チームや部署内だけでなく、他部門の社員との連携もスムーズになります。社員同士が良好な関係を築くことで、組織への帰属意識も高まり、全体的なパフォーマンスの向上につながります。
また、部署や職位を超えた活発な意見交換により、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすい環境が整います。さらに、タテとヨコの風通しが良くなることで、率直な意見交換が可能となり、業務上のミスも減少していきます。
- 離職率の低下 -
エン・ジャパン株式会社の調査によると、退職理由のトップは「職場の人間関係」であることが明らかになっています。社内コミュニケーションが活性化すると、困りごとを上司や同僚に相談しやすくなり、一人で問題を抱え込むことが少なくなります。
また、日々の業務における小さな悩みも共有できる環境が整うことで、ネガティブな感情の蓄積を防ぎ、結果として離職率の低下につながります。さらに、社員同士の信頼関係が深まることで、働きやすいと感じられる職場環境が形成され、長期的な就業継続への意欲も高まります。
参考:「本当の退職理由」調査(2024) ~エン・ジャパン「エンゲージ」調査
社内コミュニケーション活性化の取り組み事例

社内コミュニケーションを活性化させるためには、具体的な施策の導入が効果的です。近年では、オンラインツールの活用から、オフィス環境の改善まで、さまざまな取り組みが実践されています。
以下では、実際に成果を上げている企業の事例をもとに、効果的な取り組みをご紹介します。
- オンラインによるコミュニケーション活性化事例 -
TSUTAYA STORESでは、オンラインミーティングのサービスを導入し、日本全国に展開する店舗と、全国の各エリアを管掌するユニット長、そして社長をはじめとする本部スタッフとの間のコミュニケーションの活性化を推進しました。これまでは時間やコストの面で実現が難しかった店舗間会議も実施できるようになり、社員やスタッフ同士の交流が盛んになりました。
また、株式会社ウィルゲートでは、部門間のメンバーや、新入社員・先輩社員の交流を促進するため、オンラインランチ会を実施しています。大人数が参加するのではなく、4~6名単位で事前に割り振られたオンラインミーティングのURLにアクセスする仕組みです。ランチ会ではトークテーマが決められており、業務外の話題で盛り上がることで、ビジネスシーンでも円滑にコミュニケーションがとれるようになることを目的としています。
このようなオンラインコミュニケーション施策は、特に複数の拠点を持つ企業や、リモートワークを導入している企業において効果を発揮します。対面でのコミュニケーションが難しい環境下でも、気軽に情報共有や交流が可能となります。
- 社内イベントによるコミュニケーション活性化事例 -
株式会社デンソーでは、1万4,000人の従業員による予選を経て、総勢3,000人が参加する大規模な社内運動会を開催しています。本選に向けた練習を通じて業務以外の交流機会が生まれ、チームワークの醸成につながっています。
また株式会社DTSでは、健康経営とコミュニケーション活性化を目的としたウォーキングイベントを実施。歩数記録やグループチャット機能付きのアプリを活用することで、自然な形での交流が促進されています。
- 社内報やチャットなどを活用したコミュニケーション活性化事例 -
株式会社パネイルでは、従業員からの質問に答える社内ラジオを運用しています。従来は社内報の企画として社長への質問を募集していましたが、当時は紙媒体で運用していたため紙面での制約があり、一部の質問にしか答えられませんでした。そこで、ラジオ形式にすることで、多くの質問にも詳しく回答することが可能になりました。
また、シチズン時計株式会社では早くから社内SNSの仕組みを導入し、情報やノウハウの共有を行っています。メールと比べて気軽に情報共有ができ、他部署の業務についても理解が深まるなどの効果が表れています。
- オフィスデザイン見直しによるコミュニケーション活性化事例-
オフィスデザインの見直しは、物理的な環境改善を通じて持続的なコミュニケーション活性化を実現する有効な手段です。例えば、デスクをジグザグ型に配置することで、さまざまな人との接点が生まれやすくなります。また、4人1島の配置にすることで、斜め向かいの席の人とも自然な形で打ち合わせができる環境を作ることができます。
フリーアドレス制の導入も効果的な施策の一つです。固定席を持たず、その日の業務内容に応じて自由に席を選べる環境にすることで、普段交流の少ない部署の社員との新たなコミュニケーションが生まれます。さらに、オープンなミーティングスペースや商談スペースを設けることで、気軽な打ち合わせや情報交換の機会が増加します。
リフレッシュスペースの設置も重要です。カフェのような寛げる空間や、立ち話ができるスペースを用意することで、業務の合間に自然な交流が生まれます。また、コピー機やプリンターの周辺に共有の文具を設置したり、作業スペースを併設したりすることで、偶発的なコミュニケーションを促進することができます。
社内コミュニケーション活性化を成功させるポイント

社内コミュニケーションの活性化を効果的に進めるためには、計画的なアプローチが欠かせません。
以下の3つのポイントを押さえることで、持続的な成果につなげることができるでしょう。
- ・コミュニケーション不足の原因と活性化の目的を明確にする
- ・社員に取り組みを周知する
- ・長期的な視点を持って取り組む
- コミュニケーション不足の原因と活性化の目的を明確にする -
社内コミュニケーションを活性化させる前に、まず「なぜコミュニケーションが不足しているのか」という原因を特定することが重要です。原因が明確になったら、コミュニケーション活性化で得たい効果や目的を具体的に設定します。
例えば、「離職率を下げる」「部署間の連携をスムーズにする」といった明確な目標を定めることで、どのような施策を導入すべきか検討しやすくなります。多くの場合、コミュニケーション不足には複数の課題が絡み合っていますが、一度にすべての解決を目指すのではなく、最も優先度の高い課題から着手することが効果的です。
- 社員に取り組みを周知する -
社内コミュニケーション施策を導入する際は、必ず全従業員への周知を徹底する必要があります。「なぜ社内コミュニケーションを活性化するのか」という目的を明確に伝え、具体的にどのような取り組みを実施するのかを説明します。
周知方法としては、メールや社内報、掲示物など、複数の手段を組み合わせることが効果的です。また、従業員の意見を取り入れた施策であることを示し、「従業員の○○という意見をもとに△△という施策を行う」といった形で伝えることで、社員の参加意識を高めることができます。
- 長期的な視点を持って取り組む -
社内コミュニケーション施策の効果は、短期間では十分な成果が表れにくいものです。例えば、社内イベントを1度開催しただけでは、一時的な盛り上がりは得られても、数週間後には元の状態に戻ってしまう可能性があります。
そのため、さまざまな施策を組み合わせながら、効果を分析し、改善を重ねていく中長期的な取り組みが必要です。また、施策がマンネリ化して従業員のモチベーションが低下することを防ぐため、毎年異なる施策を取り入れるなど、定期的な見直しも重要です。
社内コミュニケーション活性化させるオフィス空間事例
オフィス空間のデザインは、社内コミュニケーションの活性化に大きな影響を与えます。近年では、従来の固定的なレイアウトから脱却し、より柔軟で多様な働き方に対応したオフィスづくりが注目されています。
以下では、コミュニケーション活性化を実現した先進的なオフィス事例をご紹介します。
- 日本地工株式会社様 -
.jpg?fm=webp&auto=format&fit=max&w=2048)
オフィス内食堂の改修により、多目的コミュニケーションエリアとしての機能を実現した事例です。施工面積81坪(268.3㎡)の空間に、個人での利用からグループでの利用まで対応できる多様な席を設置することで、食事や打ち合わせ、リフレッシュなど、さまざまな用途に活用できる空間となっています。
デザイン面では、東側に窓がある環境で暗くなりがちだった空間を、ライト色の建材とビビットな什器を効果的に組み合わせることで、明るく活気のある雰囲気を創出しています。また、フェイクグリーンを使用した壁面デザインやオリジナルの休憩席を設けるなど、社員が愛着を持てる工夫も施されています。
関連記事:日本地工株式会社様 食堂改修
- L.Biz日本橋 -

「住まうように働く空間」をコンセプトに、多様な働き方に対応できるオフィスとして設計されました。自宅やカフェ、ホテルなど、どこでも仕事ができる現代において、あえてオフィスで働く価値を見出せる魅力的な空間を目指しています。
デザインの特徴として、眺めの良い景色を楽しめるカウンター席、自宅のリビングのようにくつろげるソファ席、集中作業向けのデスク席、カジュアルなコミュニケーションが可能なカフェスペースなど、さまざまな執務エリアを設けています。
また、木目や石目、左官の要素を取り入れることで温かみのある雰囲気を演出しつつ、カラーの彩度を抑えることで先進的なオフィスの雰囲気も両立させています。
関連記事:L.Biz日本橋セットアップオフィス 新設
- 株式会社ロッテ様 -

フレキシブルな働き方の実現を目指し、多様なワークエリアと自由にレイアウトを変更可能な共用エリアを増設したオフィスです。特徴的なのは、遮蔽物を最小限に抑えた設計により、社員同士の自然な出会いと会話を促す工夫が施されていることです。
デザイン面では、企業のブランドカラーを差し色として効果的に使用し、企業らしさを表現しています。また、自社製品を展示できるディスプレイ棚を新設するなど、企業風土の醸成にも配慮した空間となっています。施工面積は176坪(581㎡)に及び、開放的な空間づくりにより、部署を超えた偶発的なコミュニケーションを生み出すことに成功しています。
関連記事:株式会社ロッテ様 執務室改修
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
社内コミュニケーションの活性化は、企業の持続的な成長と発展に不可欠な要素です。多様な働き方が広がる現代において、オンラインツールの活用や社内イベントの実施、オフィス環境の整備など、さまざまなアプローチで取り組むことが重要です。社内コミュニケーションを活性化させることで、社員のモチベーション向上や生産性の向上、離職率の低下といった具体的な成果を得ることができます。目的を明確にし、全社員に施策を周知したうえで、長期的な視点を持って取り組むことで、より良い職場環境を実現することができるでしょう。
TOPPANでは社内コミュニケーションを活性化させるオフィスレイアウトのご提案が可能です。
様々なワークスタイル変革に対応したオフィスをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください!
関連コラム

<TOPICS>インフォーマルコミュニケーションとは?具体例やメリット・オフィスの事例

<TOPICS>社内コミュニケーションを活性化させるアイデア|メリットと事例を紹介