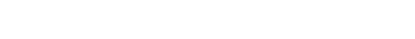<TOPICS>働きやすい職場づくりの具体的なポイントとは
労働環境とは?日本の労働問題の現状や改善策・取り組み事例を解説
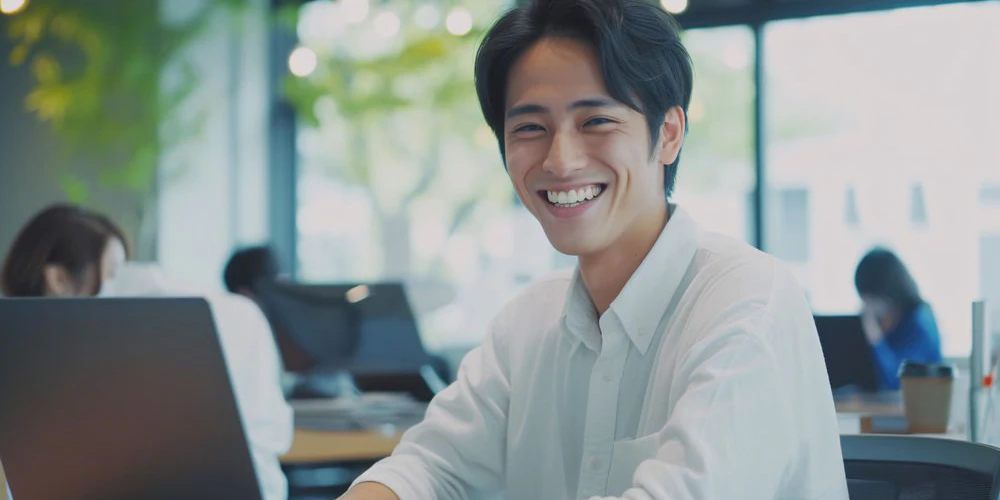
労働環境とは

労働環境とは、従業員を取り巻くあらゆる状況や条件を指します。具体的には、オフィスや作業場の物理的な環境、労働時間、人間関係、給与体系など、仕事に関連するすべての要素が含まれます。快適で安全な労働環境は、従業員の健康と生産性に直接的な影響を与えるため、非常に重要な要素となっています。
労働環境の整備は、単に従業員の満足度を高めるだけでなく、法的にも企業の義務として定められています。労働基準法特別法である「労働安全衛生法」の第3条第1項では、以下のように明記されています。
「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」
この条文は、企業が従業員の安全と健康を守るために、適切な労働環境を整備する責任があることを明確に示しています。つまり、労働環境の改善は企業の法的な義務であり、同時に従業員の生産性向上や定着率の改善にもつながる重要な経営課題なのです。
良好な労働環境を整備することで、企業は従業員の健康を守り、モチベーションを高め、結果として業績の向上につなげることができます。一方で、劣悪な労働環境は「ブラック企業」というレッテルを貼られる原因ともなり、人材確保や企業イメージに悪影響を及ぼす可能性があります。
したがって、企業は法令遵守の観点からだけでなく、長期的な成長戦略の一環として労働環境の整備に取り組む必要があります。従業員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境を整えることが、企業の持続的な発展につながるのです。
労働環境の構成要素

労働環境は複数の要素から成り立っており、それぞれが従業員の健康と安全に影響を与えています。労働安全衛生法では、これらの要素を主に以下の3つの観点から規定しています。
- ・気候的条件
- ・物理的条件
- ・科学的条件
以降では、気候的条件、物理的条件、科学的条件について説明していきます。これらの条件を適切に管理することで、従業員にとって快適で安全な労働環境を実現することができます。
- 気候的条件 -
気候的条件は、労働者の快適性や健康に直接影響を与える重要な要素です。労働安全衛生法では、気温、湿度、気圧、風速、紫外線などの気候に関連する要因を気候的条件として定めています。これらの要因は、労働者の体調や作業効率に大きな影響を与える可能性があるため、適切な管理が求められます。
例えば、夏季の高温環境下での作業は熱中症のリスクを高めます。一方、冬季の低温環境は、体の冷えや凍傷のリスクを増加させます。そのため、事業者は季節や作業内容に応じた適切な温度管理を行う必要があります。また、湿度管理も重要で、過度に乾燥した環境や高湿度の環境は、呼吸器系の問題や皮膚トラブルを引き起こす可能性があります。
さらに、屋外作業においては紫外線対策も重要です。長時間の紫外線曝露は、日焼けや皮膚がんのリスクを高める可能性があるため、適切な保護具の使用や作業時間の管理が必要となります。
事業者は、これらの気候的条件を定期的にモニタリングし、必要に応じて空調設備の導入や作業環境の改善を行うことが求められます。また、労働者に対しても、気候条件に応じた適切な服装や行動についての教育を行うことが重要です。
- 物理的条件 -
物理的条件は、労働者の身体に直接的な影響を与える環境要因を指します。労働安全衛生法では、照明、騒音、振動、粉じん、放射線などを物理的条件として規定しています。これらの要因は、労働者の健康や安全に重大な影響を及ぼす可能性があるため、適切な管理と対策が求められます。
照明に関しては、作業内容に応じた適切な明るさを確保することが重要です。暗すぎる環境は目の疲労や作業ミスを引き起こし、明るすぎる環境は眩しさによる不快感や目の疲れを招く可能性があります。事業者は、作業場所ごとに適切な照度を維持し、必要に応じて局所照明を導入するなどの対策を講じる必要があります。
騒音については、長期間の曝露が聴力障害を引き起こす可能性があります。労働安全衛生法では、騒音レベルに応じた対策を講じることを義務付けています。例えば、85デシベルを超える騒音環境では、防音設備の設置や耳栓の着用などの対策が必要となります。
振動も労働者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、手持ち工具を使用する作業では、振動障害のリスクが高まります。事業者は、低振動の機器を選択したり、作業時間を制限したりするなどの対策を講じる必要があります。
粉じんについては、長期間の吸入が呼吸器系の疾患を引き起こす可能性があります。事業者は、粉じんの発生を抑制する設備の導入や、適切な保護具の使用を徹底する必要があります。
- 科学的条件 -
科学的条件は、労働環境における化学物質や生物学的要因に関する基準を指します。労働安全衛生法では、有害物質、ガス、蒸気、粉じん、病原体などを科学的条件として規定しています。これらの要因は、労働者の健康に直接的かつ深刻な影響を与える可能性があるため、厳格な管理が求められます。
有害物質に関しては、その種類や濃度に応じた適切な管理が必要です。例えば、有機溶剤を扱う作業場では、換気設備の設置や保護具の着用が義務付けられています。また、特定化学物質を扱う作業では、作業環境測定の実施や特殊健康診断の実施が求められます。
ガスや蒸気についても、その種類や濃度に応じた対策が必要です。例えば、一酸化炭素などの無色無臭の有害ガスが発生する可能性がある作業場では、ガス検知器の設置や定期的な環境測定が義務付けられています。
粉じんについては、その種類や粒子の大きさによって健康への影響が異なります。特に、石綿(アスベスト)などの発がん性のある物質については、厳格な管理が求められます。事業者は、粉じんの発生を抑制する設備の導入や、適切な保護具の使用を徹底する必要があります。
病原体に関しては、医療機関や研究施設などで特に注意が必要です。感染症のリスクを最小限に抑えるため、適切な衛生管理や保護具の使用、廃棄物の適切な処理などが求められます。
これらの科学的条件を適切に管理することは、労働者の健康を守るだけでなく、労働災害の予防にも繋がります。事業者は、取り扱う物質や作業内容に応じた適切なリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じることが重要です。また、労働者に対しても、取り扱う物質の危険性や適切な取り扱い方法について、十分な教育を行うことが求められます。
日本の労働環境の現状|課題・問題点

日本の労働環境には、長時間労働や過労死、メンタルヘルスの悪化など、さまざまな課題が存在します。これらの問題は、労働者の健康と生活の質に深刻な影響を及ぼすだけでなく、企業の生産性や社会全体の持続可能性にも関わる重要な課題となっています。
以下では、日本の労働環境が直面する主要な問題点について解説します。
- 長時間労働や過労死が社会問題に -
日本の労働環境において、長時間労働や過労死は依然として深刻な社会問題となっています。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、労働者1人当たりの年間総実労働時間は長期的に減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあります。平成27年の調査では、前年比7時間減少し、3年連続で減少しているものの、年間1,734時間という数字は国際的に見ても高い水準です。
特に問題なのは、一般労働者の総実労働時間が2,000時間前後で高止まりしていることです。週60時間以上働く長時間労働者の割合も、平成27年時点で男性の約8.2%、女性の約2.8%に上っています。こうした長時間労働は、労働者の健康被害や過労死のリスクを高めるだけでなく、仕事と生活のバランスを崩し、生産性の低下にもつながっています。
過労死等の労災補償状況を見ると、脳・心臓疾患の請求件数は平成27年度に795件、うち支給決定件数は251件(死亡96件を含む)となっています。また、強い心理的負荷による精神障害の請求件数は1,515件、うち支給決定件数は472件(未遂を含む自殺93件)に上ります。これらの数字は、日本の労働環境における過重労働の深刻さを物語っています。
- ハラスメント問題|パワハラ・セクハラなど -
職場におけるハラスメントは、日本の労働環境における深刻な問題として注目を集めています。パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントなど、さまざまな形態のハラスメントが労働者の尊厳を傷つけ、継続就業を妨げる大きな障害となっています。
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和2年度)によると、過去3年間にパワハラの相談があったと回答した企業の割合は48.2%に上り、セクハラは29.8%、顧客等からの著しい迷惑行為は19.5%となっています。特に深刻なのは、労働者の31.4%がパワハラを経験したと回答している点です。
この状況を受け、政府は職場におけるハラスメント対策を強化しています。令和2年6月には労働施策総合推進法が施行され、企業に対してパワーハラスメントに関する防止措置を講じることが義務付けられました。また、セクハラや妊娠・出産等に関するハラスメントについても、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に基づく防止措置が求められています。
しかし、法制度の整備だけでは十分ではありません。企業には、ハラスメントを防止するための明確な方針の策定、相談窓口の設置、従業員への教育・研修の実施など、具体的な取り組みが求められています。また、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策も重要な課題となっており、業種・業態に応じた適切な対応が必要とされています。
- メンタルヘルス問題|うつ病の増加 -
近年、日本の労働環境において、メンタルヘルス問題、特にうつ病の増加が深刻な課題となっています。仕事や職業に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高まっており、心の健康障害による通院者数も増加傾向にあります。
この状況に対応するため、厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定し、事業場でのメンタルヘルス対策の実施を推進しています。この指針では、セルフケア、ラインによるケア、産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアという4つのケアを継続的かつ計画的に行うことを提唱しています。
特に注目すべきは、メンタルヘルス対策の目的が単なる安全配慮義務の履行にとどまらず、すべての労働者の心の健康レベルを引き上げることにも重点を置いている点です。また、従来型のうつ病だけでなく、近年増加している抗うつ剤が効きにくく長期化しやすいタイプのうつ病や、双極性障害、統合失調症、睡眠障害なども含めた幅広い精神疾患に対する職場適応の在り方が問題となっています。
- 賃金格差や貧困問題|非正規雇用の増加 -
日本の労働市場は、非正規雇用の増加と賃金格差の拡大という深刻な課題に直面しています。総務省の「労働力調査」によると、非正規雇用労働者の割合は年々増加傾向にあり、2023年には全雇用者の37.1%を占めるまでに至っています。
この非正規雇用の増加は、労働市場に大きな影響を与えています。特に顕著なのは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の賃金格差です。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、正社員・正職員の平均月額賃金が32万8,000円であるのに対し、非正規雇用労働者のそれは22万1,300円と、約10万円もの差が生じています。
さらに、この賃金格差は男女間でも顕著です。正社員・正職員の男性の平均月額賃金が35万3,600円であるのに対し、非正規雇用の女性は19万8,900円と、その差は15万円以上に及びます。
このような状況は、労働者の生活の質や将来の経済的安定性に大きな影響を与えかねません。特に、65歳以上の高齢者の非正規雇用が増加している点は、年金制度との関連で今後さらなる社会問題となる可能性があります。
非正規雇用の増加と賃金格差の問題は、日本の労働環境における喫緊の課題であり、政府や企業による積極的な取り組みが求められています。
参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構|一般労働者の月額賃金における男女格差が2年連続で縮小
- 人材不足が深刻化|労働人口減少の影響 -
日本の労働環境において、最も深刻な問題の一つが人材不足です。この背景には、少子高齢化による労働人口の減少があります。2021年の労働力人口は6,860万人で、前年に比べ8万人減少し、2年連続の減少となりました。特に、15~64歳の労働力人口は5,931万人と、15万人も減少しています。
この労働力人口の減少は、産業界全体に大きな影響を与えています。例えば、「宿泊業,飲食サービス業」では22万人、「建設業」では10万人の就業者数が減少しており、人手不足が深刻化しています。一方で、「医療,福祉」分野では22万人の増加が見られ、高齢化に伴う需要の増加が反映されています。
労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は62.1%と、わずかに上昇していますが、これは女性や高齢者の労働参加が進んでいることを示しています。しかし、この上昇だけでは労働力不足を補うには十分ではありません。
人材不足は企業の生産性低下や経済成長の鈍化につながる重大な問題です。この課題に対応するためには、労働環境の改善や働き方改革、さらには外国人労働者の受け入れなど、多角的なアプローチが必要となっています。
参考:統計局|労働力調査 令和3年平均結果の概要 Ⅰ 基本集計
労働環境を改善するための対策事例

労働環境の改善は、従業員の生産性向上や定着率アップにつながる重要な取り組みです。企業によって最適な方法は異なりますが、一般的に効果的とされる対策をいくつかご紹介します。
これらの事例を参考に、自社の状況に合わせた労働環境改善策を検討してみましょう。
- 柔軟な働き方を導入する -
柔軟な働き方の導入は、従業員一人ひとりのライフスタイルに合わせた就業を可能にし、ワークライフバランスの向上につながります。具体的には、リモートワークやフレックスタイム制、時短勤務などの制度を設けることが挙げられます。
これにより、育児や介護といった個人の事情に対応しやすくなり、優秀な人材の確保や離職率の低下が期待できます。また、従業員の満足度やモチベーション向上にもつながり、結果として生産性の向上にも寄与します。
- メンタルヘルス対策を実施する -
メンタルヘルス対策は、従業員の精神的な健康を維持・向上させるために欠かせません。具体的な取り組みとしては、セルフケアの促進、管理職によるラインケア、産業医や保健師による相談体制の整備などがあります。
また、ストレスチェックの実施や、外部の専門家と連携したケアプログラムの導入も効果的です。メンタルヘルス対策を充実させることで、うつ病などの精神疾患の予防や早期発見・対応が可能となり、長期休職や離職のリスクを軽減できます。
- 多様な人材を登用する -
多様な人材の登用は、企業の創造性や競争力を高める重要な施策です。性別や年齢、国籍、障害の有無にかかわらず、幅広い人材を採用・活用することで、多様な視点や経験を組織に取り入れることができます。
例えば、女性や高齢者、外国人労働者の活躍を促進する制度の導入や、障害者雇用の推進などが考えられます。多様性を尊重する職場環境は、従業員の相互理解を深め、イノベーションを生み出す土壌となります。
- 従業員アンケートを実施する -
従業員アンケートの実施は、労働環境の現状把握と改善点の発見に有効です。定期的にアンケートを行うことで、従業員の満足度や不満、要望を直接聞くことができます。匿名性を確保し、率直な意見を集められるよう工夫することが大切です。
収集した意見をもとに具体的な改善策を講じることで、従業員の声が反映された働きやすい環境づくりが可能になります。また、自分の意見が会社に届いているという実感が、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
- 休暇や福利厚生の利用を促進する -
休暇や福利厚生の積極的な利用促進は、従業員のリフレッシュや健康維持に重要です。有給休暇の取得率向上を目指すほか、独自の特別休暇制度の導入なども効果的です。
例えば、連続休暇の取得を奨励したり、リフレッシュ休暇を設けたりすることで、従業員の心身のリラックスを図ることができます。また、福利厚生施設の利用促進や、健康診断の充実なども、従業員の生活の質向上に寄与します。これらの取り組みは、従業員の満足度向上と、長期的な生産性の維持・向上につながります。
- ITツールの導入で業務効率化を図る -
ITツールの導入は、業務効率化と労働時間の削減に大きな効果をもたらします。例えば、Web会議システムの活用により、移動時間の削減や遠隔地とのスムーズな情報共有が可能になります。また、勤怠管理システムやビジネスチャットツールの導入により、業務の進捗管理や社内コミュニケーションが円滑になります。
さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用で、定型業務の自動化も実現できます。これらのツール導入により、従業員は創造的な業務に注力できるようになり、労働生産性の向上が期待できます。
- コミュニケーションを活性化する -
職場でのコミュニケーション活性化は、良好な人間関係の構築と情報共有の促進に重要です。具体的な取り組みとしては、定期的な1on1ミーティングの実施や、部署横断的なプロジェクトチームの編成などが挙げられます。また、社内イベントの開催やオープンスペースの設置も、インフォーマルなコミュニケーションの機会を増やす効果があります。
活発なコミュニケーションは、従業員間の相互理解を深め、協力体制の強化につながります。結果として、職場の雰囲気が改善され、業務効率の向上にも寄与します。
- オフィス環境を整備する -
快適なオフィス環境の整備は、従業員のパフォーマンス向上に直結する重要な要素です。適切な照明、温度管理、座席レイアウト、休憩スペースの確保など、物理的な環境を整えることで、従業員の集中力と生産性を高めることができます。
具体的な整備内容としては、まず業務に必要な基本的な設備であるデスクやチェアの品質向上が挙げられます。長時間のデスクワークによる身体的負担を軽減するため、人間工学に基づいた家具の選定が重要です。また、適切な照明設備やエアコンの設置により、目の疲れや体調不良を防ぐことができます。
さらに、リフレッシュスペースやミーティングスペースなど、従業員が柔軟に活用できる共有スペースの設置も効果的です。こうした空間は、従業員同士のコミュニケーションを促進し、創造性を高める効果があります。定期的な設備点検と更新も欠かせません。労働環境の改善は一度きりの取り組みではなく、継続的なメンテナンスと見直しが必要です。
労働環境改善につながるオフィスレイアウト例
労働環境の改善において、オフィス環境の整備は非常に重要な要素です。適切なレイアウトや設備は、従業員の生産性向上やコミュニケーションの活性化、さらにはウェルビーイングの促進にも大きく寄与します。
以下に、実際のオフィスレイアウト改修事例をご紹介します。これらの事例から、従業員のニーズに合わせた柔軟な空間づくりや、コミュニケーションを促進する仕掛けなど、労働環境改善のヒントを得ることができるでしょう。
- 株式会社文昌堂様 -



株式会社文昌堂様のオフィス改修事例では、「Paper links history」という基本理念を反映し、従来の風通しの良い企業風土を維持しつつ、歴史と新しい感性を融合させた空間を創出しました。特筆すべきは、7階をABWを取り入れたコミュニケーション促進エリア、8階を執務エリアとして階層で役割を分けた点です。この工夫により、業務内容や目的に応じて柔軟に働ける環境が実現しました。
さらに、マグネットウォールやオープンラックの設置により、情報共有や社内外へのPRも容易になり、従業員の満足度向上につながる空間が生まれています。
関連記事:株式会社文昌堂 様 オフィス改修
- NC建材株式会社様 -


NC建材株式会社様のオフィス営業所新設では、多様な業務スタイルに対応しつつ、企業の魅力を伝える"魅せるオフィス"を実現しました。エントランスにはプロジェクションマッピングを用いた印象的な企業ロゴを配置し、来訪者を温かく迎え入れる工夫がなされています。執務室では、ゾーンごとに明るいカラーを配置し、活気ある雰囲気を演出。
さらに、オープンスペースやカフェブース、個別ミーティングブースなど、多様な作業環境を用意することで、従業員が状況に応じて柔軟に働ける空間を創出しています。
関連記事:NC建材株式会社様 オフィス営業所新設
- 日本地工株式会社様 -


日本地工株式会社様の食堂改修事例では、暗さという課題を解決するため、ライト色の建材とビビッドな什器を活用し、明るく活気ある空間を実現しました。多様な席を設けることで、食事だけでなく打ち合わせやリフレッシュなど、多目的に活用できるコミュニケーションエリアとしての機能も持たせています。
さらに、同社のフェイクグリーンを使用した壁面デザインやオリジナルの休憩席を設置するなど、従業員の愛着を育む工夫も施されています。これらの改善により、従業員が活き活きと利用できる魅力的な空間が生まれ、職場環境の質的向上に貢献しています。
関連記事:日本地工株式会社様 食堂改修
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
労働環境の改善は、企業の持続的な成長と従業員の幸福度向上に不可欠です。長時間労働やハラスメント、メンタルヘルス問題など、日本の労働環境には多くの課題がありますが、これらを解決することで生産性の向上や優秀な人材の確保につながります。柔軟な働き方の導入やダイバーシティの推進、ITツールの活用など、さまざまな対策を講じることで、従業員にとって魅力的な職場環境を創出できます。さらに、オフィスレイアウトの工夫により、コミュニケーションの活性化や業務効率の向上も期待できます。労働環境の改善に取り組むことで、企業の競争力強化と従業員の満足度向上を同時に実現することができるのです。
TOPPANでは従業員にとって魅力的な職場環境につながる、オフィスレイアウトのご提案が可能です。
オフィスレイアウトの工夫により従業員のコミュニケーションをさらに活性化したい際は、ぜひお気軽にご相談ください!
関連コラム

<TOPICS>ハイブリッドワークとは?導入のメリット・デメリットや事例もご紹介!

<TOPICS>働きやすい職場とは?働きやすい職場環境の特徴やメリットを紹介