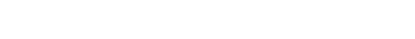<TOPICS>執務スペースを十分に確保できない場合の対処法も解説!
執務スペースとは?デザインする際のポイントや改修・新設事例を紹介

執務スペースとは

執務スペースとは、オフィス内でPCワークや資料作成など、集中して業務を行うための席や場所のことです。執務エリアと呼ばれることもあります。
固定席があるオフィスでは自分の席で業務を行うのが通常ですが、固定席がないフリーアドレスオフィスや、業務の内容に合わせて働く場所を自由に働く場所を選択するABW(Activity Based Working)を採用している場合には、集中して働くための執務スペースは必須です。
また、リモートワークやハイブリッドワーク、ノマドワークなど働き方が多様化することで出社率に変化が見られるようになった昨今、オフィスの使われ方も変化してきました。それに伴い、執務スペースに求められる役割も変わりつつあります。
単に業務ができるスペースを確保するだけでなく、自社が採用する働き方の特徴に合わせて工夫する必要があります。例えば、リモートワーク率が高い会社の場合、オフィスを対面コミュニケーションの場ととらえ、執務スペース内にミーティングや会話がしやすい空間を導入すると社内の活性化につながるでしょう。
- 事務室との違い -
業務を行う際に使用するスペースを「事務室」と呼ぶ会社も多いですが、オフィスにおいて執務スペースと事務室の違いは基本的にはありません。「執務=事務処理」を意味するからです。そのため、執務スペースや事務室は同じく業務を処理するための席が配置されたスペース(部屋)だと考えて構いません。
執務スペースをデザインする際のポイント

執務スペースをデザインする際には、以下のポイントを意識することが大切です。
- ・適切な広さを確保する
- ・シンプルな動線を意識する
- ・自社に応じたデスクのレイアウトを検討する
それぞれのポイントについて、具体的に見ていきましょう。
- 適切な広さを確保する -
執務スペースをデザインする際には、適切な広さを確保することが重要です。特に、一人当たりの面積がしっかり確保していないと、従業員に物理的・精神的ストレスを与えかねません。そのような状況では業務効率や生産性を著しく低下させてしまうでしょう。
反対に、必要以上に広くても賃料や冷暖房費などコスト上のムダが大きくなります。そこで、従業員一人当たりの広さの目安を把握しておき、適切な執務スペースの広さを検討することが必要です。
では、従業員一人当たりの面積の目安はどのくらいなのでしょうか。この点、労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則によると、一人当たり約1.4坪(4.8㎡)以上確保する必要があります。ただし、この数値には設備類が含まれるので、実際には約1坪が最低ラインと考えてください。
一方、オフィス家具メーカーの多くは一人当たり約2~4坪(約6.6~13.2㎡)の広さを推奨しています。ただし、企業の規模、営業・事務・技術などの職種によって執務スペースの利用方法が異なる点に注意が必要です。実際の広さを検討する際には、職種ごとの利用方法やオフィス全体の面積、従業員数や出社率なども考慮する必要があるでしょう。
- シンプルな動線を意識する -
執務スペースをデザインする際には、従業員が使いやすいよう実際の動線を考慮しなければなりません。動線とは、目的地までの移動経路を線の形で表すものです。例えば、エントランスから執務スペースへのアクセス経路、ロッカーやコピー機・シュレッダー、棚などの設備へのアクセス経路などが該当します。
動線が複雑になると、コミュニケーションが取りにくくなり、ムダな動きが増えてしまいます。そこで、できるだけシンプルかつ利用しやすい動線を確保することが大切です。
動線を検討する際には、以下の点に特に注意してください。
- ・ストレスなく移動できるか
- ・オフィス内の各設備へアクセスしやすいか
例えば、エントランスから自分の執務スペースに行くのに迂回する動線だけしかないと、業務を始める段階でストレスがたまるでしょう。また、狭い場所に席が配置されていると周囲とのコミュニケーションが取りにくく、業務効率が下がってしまいます。
さらに、様々なオフィス設備や家具が設置されていますが、これらが動線から外れていると利用する際にムダな移動が発生します。
執務スペースの動線を検討する際には、シンプルな経路でストレスなく移動できるかどうか意識しましょう。また、頻繁に使うオフィス設備や家具をメイン動線上に設置する、使用頻度が低い場合でも通り抜け可能なサブ動線に設置するなどの配慮も必要です。
- 自社に応じたデスクのレイアウトを検討する -
執務スペースのデザインでは、デスクのレイアウトがカギを握ります。自社の業務の特徴を把握した上で、デスクを配置しましょう。執務スペースの広さや業務内容によって適したレイアウトは異なります。
デスクのレイアウトの種類とそれぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
デスクのレイアウトの種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
対向型 |
|
|
同向型 |
| ある程度広さが必要 |
背面型 |
|
|
左右対向型 |
|
|
業務の内容に合わせて、コミュニケーションの範囲や適した距離などが変わってきます。また、レイアウトによってはある程度の広さを確保しなければならないため、スペースとの兼ね合いも考慮して検討しましょう。
デスクのレイアウトや運用方法については、以下の記事も参照してください。
オフィスレイアウトの種類とは?各レイアウトのメリット・デメリットを解説
執務スペースを十分に確保できない場合の対処法

執務スペースのデザインを検討しようとしても、スペースを十分に確保できないケースもあるかもしれません。ここでは、執務スペースを十分に確保できない場合の対処法についてご紹介します。
- ペーパーレス化を進める -
まず挙げられるのが、ペーパーレス化を進めて紙の書類を削減し、保管スペースを縮小することです。書類の保管スペースを別の用途に活用できるので、ぜひ検討してみてください。
執務スペースのデザイン検討を機に、文書管理の方法を見直してみることをおすすめします。具体的な方法は、以下の通りです。
- ・社内文書の電子化を進める
- ・紙で作成する場合には両面印刷にする
- ・紙の文書の保存期間を決め、期間が満了したら廃棄・データ化する
社内文書の電子化を進めれば、業務効率化も図れます。特にテレワークを推奨している企業にとってはオンラインで書類を共有できると利便性が大きく上がるでしょう。
ただし、いきなりすべての社内文書を電子化するのは難しいかもしれません。文書管理のルールを定め、徐々にペーパーレス化を進めていくのがおすすめです。
- 共有スペースを複数の用途で使用する -
共有スペースを複数の用途で使用することも、執務スペースを確保するために有効です。例えば、打ち合わせや来客対応、食事、休憩など、共有スペースに複数の役割を持たせると、個別にスペースを用意する必要がありません。用途ごとに利用時間帯を決めておくとバッティングすることもないでしょう。
共有スペースでは、机やいすをキャスター付きにするなどレイアウトを変更しやすいようにしておくのがおすすめです。共有スペースの運用を見直すだけで対応できる場合もありますが、用途に合わせて一部オフィス家具の入れ替えが必要な場合もあるかもしれません。
ただし、休養室のように、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、事務所衛生規則などで必ず設置しなければいけないスペースもあるので、法令をしっかり確認し、必要に応じて労働基準監督署や社会保険労務士、オフィスづくりの専門会社に相談してください。
- コンパクトな家具を選ぶ -
コンパクトな家具を選ぶことにより、執務スペースを確保することも可能です。
執務スペースのデスクのスタンダードな大きさは、幅120~150cm×奥行70cmです。しかし、業務内容によってはそれより小さくても支障が出ないこともあります。
例えば、主にノートパソコンを使用して資料を作成する部署では、コンパクトなサイズのデスクやフリーアドレス制を導入することで、執務スペースを確保できるでしょう。反対に、多くの資料や大きな図面などをデスク上に広げることが多い設計やデザインなどの部署では、大きめのデスクが必要です。
また、背の高い家具が執務スペースの中央に置かれていると、圧迫感を与えます。これに対し、背の低い家具を選べば目線を遮られずに執務スペース全体を見渡せるため、広くすっきりした印象を与えられるでしょう。視覚的にスペースを広く感じさせる家具を選ぶことも有効な方法です。
執務スペースの改修・新設事例
続いて、執務スペースの改修・新設事例をご紹介します。執務スペースのデザインを検討する際の参考にしてください。
- 株式会社ロッテ様 -

最初にご紹介するのは、株式会社ロッテ様の執務室改修事例です。
フレキシブルな働き方の実現のために、多様なワークエリアや自由にレイアウトを変更できる共用エリアを増設しました。遮蔽物の少ない石器画にすることで、偶発的なコミュニケーションを生む空間に仕上げています。
また、「ロッテ様らしさ」を表現するために、ブランドカラーを差し色に使用しました。自社製品などを陳列できるディスプレイ棚を新設するなど、企業風土の醸成を促すような仕掛けも施しています。
- NC建材株式会社様 -

オフィス営業所の新設事例です。気分や状況に応じて柔軟に働くことができるオフィスを実現しています。
NC建材株式会社様からは、多様な業務スタイルを実現するとともに、働きたくなる「魅せるオフィス」にすることで、企業の魅力を伝えられるようにしたいというご要望がありました。
そこで、エントランス正面の企業ロゴにはシンボリックなプロジェクションマッピングを設け、お客様に気持ちよく来訪していただける仕掛けを演出。来客エリアと執務エリアの仕切りにはガラスとルーバーを使用し、エントランスからも内部の活気や雰囲気が伝わるよう工夫しました。
執務室には、オフィス内に活気が生まれるような明るいカラーをゾーンごとに配置。椅子のカラーも合わせて統一感のあるデザインにしました。ナチュラルな木目と、カラフルでポップな配色により、明るく働きやすい空間にしています。オープンスペースにはモニター付き造作棚を大きく構え、お客様や社員の方が企業のニュースリリースや商材情報などをチェックできるようにし、コミュニケーションを促すような設計にしました。
加えて、通常の打ち合わせはもちろん、気軽なミーティングやオンラインでの打ち合わせが可能な個別ブースも設置。オフィスの隅に位置するカフェブースは、執務室とは異なる落ち着いた雰囲気で、スライディングウォールを用いれば大人数に対応できる会議室としても利用が可能です。
- 株式会社エー・アール・シー様 -

株式会社エー・アール・シー様のオフィス移転の事例です。「人と人のつながりを持てる温かいオフィス」をコンセプトに、シームレスにオフィス内を見渡せる空間を目指しました。
温かみのある素材をベースに、コーポレートカラーであるオレンジと植栽のグリーンを差し色にすることで、働きやすさや居心地の良さを追求。また、スケルトン天井にすることで、開放感のある広々とした空間を演出しました。
床をシームレスにつないだデザインを採用し、カフェエリアと執務エリアの境界線をあえて曖昧にすることで、カフェエリアもフリーアドレス席として利用できるよう工夫を施しています。
- 名駅南オフィス様 -

オフィス営業所の新設事例です。営業効率や出張時の利便性向上、新入社員のリクルートにもつながるオフィスにしたいというご要望がありました。
エントランスは、もともとあった蛍光灯を撤去し、すべてダウンライトに変更。色温度を一般的なオフィスより下げることで、ホテルライクで上質な空間とし、来訪者の方に企業のブランドが伝わるようなエントランスに仕上げています。
執務室につながる自動ドアは斜めに設置し、ドアが開いた際に執務室が正面に見えるようにすることで、空間が広く感じられるよう工夫を施しました。
執務室の什器は黒と白で統一し、スタイリッシュな空間を演出。左側はあえてスペースに余裕を持たせ、将来的にデスクや打ち合わせスペースを増設できるようにするなど、可変性を意識した作りです。また、執務室の一角にはウェブ会議や週ちゅう作業に最適な「セミクローズブース」をご提案。手元の照度にもこだわり、快適に使用できるようにしています。
また会議室はガラスパーテーションを使用することで、空間に圧迫感を与えないようにしています。
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
執務スペースは、オフィス内で集中して業務を行うための席や場所のことです。働き方の多様化に伴ってオフィスの利用方法、そして執務スペースのあり方も変化してきました。執務スペースをデザインする際には適切な広さを確保し、シンプルな動線を意識することが欠かせません。その上で、自社の状況に合わせてデスクのレイアウトを検討しましょう。
また、執務スペースを確保するためには、ペーパーレス化の推進や共有スペースの利用方法の見直しなどの視点が欠かせません。今回ご紹介した改修・新設事例も参考にしていただき、使いやすさを兼ね備えた執務スペースをデザインしてみてください。
TOPPANではオフィスの改修・リニューアルはもちろんのこと、オフィスレイアウトに関するご相談も承っております。働きやすいオフィスレイアウトをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください!
(※本記事に記載された相場はあくまでも目安であり、諸条件に応じて大きく変動する可能性がございます)
関連コラム

<TOPICS>オフィスレイアウトの種類とは?各レイアウトのメリット・デメリットを解説

<TOPICS>おしゃれな事務所レイアウト事例6選|配置の基本やポイント、注意点を解説!