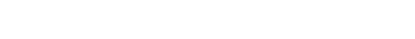オフィス移転の際の原状回復工事で気をつけるべきポイントをご紹介!
オフィスの原状回復工事とは?流れや費用を抑えるコツ・注意点を解説!

原状回復工事とは

オフィスの原状回復工事は、賃貸契約終了時に、建物や設備を入居前の状態に戻すための作業です。退去後、オーナーが新たなテナント迎えるために、入居中にできた汚れや傷を直し、建物の内装や設備をきれいな状態にします。
具体的な工事例として、以下が挙げられます。
- ・壁や天井の塗装
- ・床のクリーニングと補修
- ・ 照明器具の取り外しと交換
- ・空調設備の点検と修繕
オフィスと一般的な居住用の賃貸住宅の原状回復では、その範囲が異なります。居住用の賃貸住宅では、故意や過失ではない自然に起きる損耗や経年劣化は原状回復の範囲外となりますが、オフィスの場合はこの限りではありません。
賃貸借契約により、テナントとオーナー(借主と貸主)の負担範囲をあらかじめ定めておくことが一般的です。借主と貸主のどちら側に原状回復を行う責任があるのかについては、賃貸借契約の確認が必要になります。
-現状回復との違い-
現状回復とは、「今の状態に戻すこと」という意味合いになります。退去時に、今の状態に戻すとなると汚れや傷が残ったままになってしまうため、賃貸借契約においては「現状回復」という言葉自体、正しいものとは言えません。
「初めの状態に戻す」という意味の「原状回復」という表現が正しいでしょう。
-原状復帰との違い-
一方で原状復帰とは、「元の状態に復帰させる」という意味なので、「原状回復」と同じ意味の言葉です。そのため、原状回復と同じように世間一般では使えます。
ただし、賃貸借契約など法律の観点からは「原状回復」を用いることが多いです。「原状復帰」は建設業で使われることが多く、原状回復させるための作業(行為そのもの)を指して使われます。
原状回復工事の工事区分

原状回復するための工事には、いくつかの区分があります。工事区分はA工事・B工事・C工事の3つです。
工事の区分によって、「工事業者を選ぶのは誰か」「工事業者に発注するのは誰か」「費用を負担するのは誰か」が決まります。この違いを理解しておかなければ、退去時にどこまで原状回復に責任を持つべきか分からなくなってしまうでしょう。
工事区分による違いを以下にまとめました。
工事区分 | 対象範囲 | 工事業者の選定者 | 工事業者への発注者 | 費用負担者 |
|---|---|---|---|---|
A工事 | 建物の外装・外壁、エレベーター、共有トイレ、消防設備など | オーナー | オーナー | オーナー |
B工事 | 空調設備、照明設備、防災設備など | オーナー | テナント | テナント |
C工事 | 内装、コンセントや照明器具、配線、会社名や部署名の案内表記など | テナント | テナント | テナント |
-A工事 -
-A工事 -
A工事は、建物の共有部分を対象にする工事です。
【対象範囲の例】
- ・建物の外装・外壁
- ・エレベーター
- ・共有トイレ
- ・消防設備
A工事はオーナーがすべて工事業者の選定から費用負担まで担当します。また、入居中にエレベーターが故障して使えないなど共有部分に問題が起きた場合、テナントは修繕をオーナーに求めることが可能です。
-B工事-
B工事は、「テナントの専有部分だが、建物全体に関係するもの」を対象にする工事です。
【対象範囲の例】
- ・空調設備
- ・照明設備
- ・防災設備
B工事における工事業者の発注と費用負担はテナント側で、工事業者の選定のみオーナー側が担当します。そのため、テナント側は工事業者を自由に選べません。なぜなら、B工事は建物全体に大きな影響を与えるため、その所有者であるオーナーに工事業者を選ぶ権利があるためです。
-C工事-
C工事は、入居者の専有部分(オフィス部分)を対象とした工事です。
【対象範囲の例】
- ・内装(クロスや床のタイル、家具など)
- ・コンセントや照明器具
- ・配線(電話やインターネットなど)
- ・会社名や部署名の案内表記
C工事はすべて入居者に業者選定から費用負担までの責任があります。工事内容についてオーナーの承諾が必要とはなりますが、内装を自由にアレンジすることも可能です。ただし、原状回復できるように工夫して工事をする必要があるでしょう。
関連記事:A工事・B工事・C工事の違いとは?費用を抑えるコツや注意点を解説
原状回復工事の流れ

ここからは、原状回復工事をする際の流れについて解説します。
- 1.賃貸借契約書を確認する
- 2.施工業者に現地調査を依頼する
- 3.見積もりとスケジュールを確認する
- 4.発注・着工する
- 5.物件を引き渡す
①賃貸借契約書を確認する
テナントが負担する原状回復工事については、賃貸借契約書で定められていることが一般的です。
原状回復義務の範囲や工事区分、工事の期限、工事ができる日時などを確認するため、賃貸借契約書の内容を詳細に理解することから始めましょう。
ここを正しく理解しておかないと退去直前になってから追加の工事が発生したり、費用負担が増えたりするかもしれません。賃貸借契約書に書かれている文言の解釈が難しい場合は、オーナーや管理会社、専門家に確認するといいでしょう。
また、オーナーに対して退去の申し出をするタイミングについても前もって確認しておくとトラブルがありません。
②施工業者に現地調査を依頼する
賃貸借契約書により施行業者が指定されている場合、その施行業者に問い合わせて現地調査を依頼しなければなりません。現地調査では、立ち合いが必要となります。物件の所在地や間取り、状態など、オフィスに関する情報を前もって伝えておくと調査がスムーズになるでしょう。
なお、施工業者の指定がない場合には、自社で施工業者を選ぶところから始める必要があります。選定のためにスケジュールにゆとりをもたせておくと安心です。
③見積とスケジュールを確認する
現地調査では、施工業者にオフィスの状態を確認してもらい、原状回復の範囲をすり合わせします。工事内容で認識の違いがないよう、細かく確認しておきましょう。
そこから工事費用の見積もりと、開始日から完了日までのスケジュールを作成してもらいます。入居している建物の都合(工事の騒音が他のテナントに迷惑をかけるなど)により、作業できない日時があるケースもあるので、オーナーにもスケジュールの確認をとっておくといいでしょう。
ちなみに、オフィスの規模や建物・設備の傷み具合によって、工事に必要な期間は変わってきます。オフィス規模が大きい場合や内装を作り込んでいる場合は、工事に1ヶ月以上を要すこともあるため、できるだけ早めに施工業者に問い合わせしておくことが大切です。
④発注・着工する
施工業者に正式に発注し、着工してからは工事の進み具合をスケジュールと照らし合わせながら確認します。
トラブルを避けるために口頭やメールで報告を受けるだけでなく、現地を確認するといいでしょう。また、工事の箇所によっては施工完了後には見えなくなることもあるので、完了前に確認する必要があります。
⑤物件を引き渡す
無事、原状回復工事が完了したら、オーナーに物件を引き渡します。もし、追加で工事が必要となる場合に備えて、工事が完了する直前にオーナー立ち会いのもと、工事内容に相違がないか確認しておくと安心です。
原状回復工事の費用相場

オフィスの原状回復工事費用は、その規模によって異なります。
一般的な相場は以下のとおりです。
オフィス規模 | 1坪あたりの相場費用 |
|---|---|
小規模 | 30,000〜50,000円 |
中規模 | 50,000〜70,000円 |
大規模 | 70,000〜120,000円 |
上記は一般的な相場で、実際の工事内容や地域によって異なるかもしれません。とはいえ、オフィス規模が大きくなるほど、1坪あたりの費用は高くなっていきます。
1坪あたりの費用が数万円違うだけでも、オフィス規模が100坪、200坪となれば、百万円単位で総工費が変わってくるため、費用を抑えるコツを理解しておくことが重要です。
原状回復工事の費用を抑えるコツ

以下では、原状回復工事の費用を抑えるコツについて解説します。
【工事区分を変更する】
オーナーが工事業者を指定する「B工事」からテナントが工事業者を選べる「C工事」に、工事区分を変更できないか相談する方法です。工事業者が決まっていると高い金額で見積もりを出されることもありますが、C工事に変更できた場合テナント側で相見積をとることができ、適切な価格を把握することができます。
【複数業者から相見積もりを取る】
C工事で工事業者を選べる場合は、必ず相見積もりを取りましょう。業者間で価格を競ってもらい、より安いところに発注します。ただし、費用が安すぎると工事の質が落ちる可能性もあるため、相場費用から著しく離れた見積もりには注意してください。
【価格交渉をする】
工事業者から出された見積もりが高くなっていないか、次のような観点でチェックしてみてください。「責任の範囲外である工事が含まれていないか」「照明器具やブラインドが必要以上にグレードアップされていないか」、「共有部分の養生や資材が過剰ではないか」などです。素人目には判断が難しいため、価格交渉を専門家に依頼することも方法の一つです。
【工事のスケジュールにゆとりを持たせる】
引き渡し1ヶ月前になってから工事業者に見積もりを取りはじめ、ギリギリのスケジュールで工事を進めると、価格交渉や人材確保が難しくなり費用は高くなりがちです。できるだけスケジュールにゆとりを持たせ、引き渡しの数ヶ月〜半年前か工事業者とのやりとりを進めるといいでしょう。
【定期的なメンテナンスや設備の保護】
原状回復は建物・設備のダメージが大きいほど、費用がかさんでしまいます。そこで、入居中に定期的なメンテナンスをしたり、壁や床など傷つきやすい箇所に保護シート・マットを設置したりして、建物や設備をきれいに保つことが重要です。工事の内容や範囲を軽くすることができ、総工費を減らせるでしょう。
【自分たちで原状回復する】
照明や家具、什器の撤去など、簡単な作業を自分たちでして費用を減らすことも選択肢の一つです。ただし、契約で定められた原状回復の基準を満たす必要があり、作業内容によって建物・設備をかえって傷つけるリスクも伴うので、安易に行うことは避けるべきでしょう。
こうしたコツを実践することで、オフィスの原状回復費用を抑えられます。ただし、契約条件を守ることが重要であるため、賃貸借契約書の内容を必ず確認してください。
原状回復に関する注意点

オフィスの原状回復工事では、気をつけるべきポイントがいくつかあります。
特に注意したいポイントを、以下で解説します。
-オフィス移転の多い時期は避ける -
オフィス移転の多い時期に工事を依頼すると、工事のスケジュールが詰まって希望する期間内に工事が完了しなかったり、閑散期に比べて費用が高くなったりする可能性があります。オフィス移転の多い時期は、春(1〜3月)や秋(9〜12月)です。これは、3月や10月に決算を迎える企業が多く、決算期に移転を計画するためです。また、新年度を迎えて落ち着いた5月もオフィス移転の多い時期となります。これらの時期を避けた夏(6〜8月)が、オフィス移転の少ないタイミングと言えるでしょう。業務上可能であれば、夏を狙って退去までのスケジュールを立ててはいかがでしょうか。
- 支払いタイミングを確認する -
原状回復工事の業者によって支払いタイミングは異なります。工事前に全額支払いを要求する業者もあれば、着工前と完了後に半額ずつ支払いを求める業者もあります。
支払いタイミングについては、契約前にきちんと確認することが重要です。支払いタイミングが明確であれば、トラブルを避けられるでしょう。
まとめ
今回はオフィスの原状回復工事について工事区分や全体の流れ、費用相場、費用を抑えるコツ、注意点について解説しました。まずは賃貸借契約書の内容を細かく確認することから、退去の準備を始めましょう。スケジュールが詰まるほど費用負担やトラブルも起きやすくなるため、できる限りスケジュールにはゆとりを持たせておくことが大切です。
さいごに
オフィス移転の際は、デザインと工事を一括で行う業者を選ぶとスムーズです。
TOPPANでは調査・企画~設計・施工まで一気通貫でオフィスづくりをサポートいたします。
オフィスのレイアウト・内装デザインはもちろんのこと、拠点の構想・企画に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
関連コラム

<TOPICS>A工事・B工事・C工事の違いとは?オフィス移転の際に費用を抑えるコツや注意点を解説

<TOPICS>オフィス移転の流れとは?必要な手続きやよくあるミスを解説