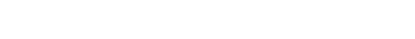<TOPICS>競争力のある組織づくりと従業員の成長に繋げるコツをご紹介
職場で心理的安全性を確保するメリットは?高める方法やパワハラとの関係性も

心理的安全性とは

心理的安全性とは、組織において自身の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことです。
そもそも心理的安全性は、心理学用語「サイコロジカル・セーフティ(psychological safety)」を日本語に翻訳したもの。1999年にハーバード大学の組織行動学研究者であるエイミー・C・エドモンドソン教授によって提唱されました。
単に職場の人と仲が良い、会議中には自由に発言するようルールを決める、といったことだけで心理的安全性は確保されません。従業員同士が、どのような発言・行動をとっても対人関係に悪い影響がないと信じて安心できるかどうかが、心理的安全性の核心です。
以下に心理的安全性が高い職場と、心理的安全性が低い職場の一例を紹介します。
■心理的安全性が【高い】職場の例
Aさんは日頃から意見交換を推奨している部署だと感じていたため、恐れずに別の方法を提案しました。そうすると上司から、新しいアイデアを歓迎されました。
■心理的安全性が【低い】職場の例
Bさんは以前に何気なく発言したことで、理由もなく叱られた経験があったため、何も言わずに上司の提案をただ受け入れました。
- ぬるま湯組織との違い -
ぬるま湯組織とは、刺激や緊張感のない、居心地が良いだけの組織を指します。具体的には、職場に緊張感がなく、業務に対する意識が低く、成長しようという意欲に欠け、チーム内でのコミュニケーションが少ない状態のことです。
心理的安全性の高い組織とぬるま湯組織の違いは、意見の対立や建設的な議論の有無にあります。心理的安全性の高い組織では、メンバーが自由に意見を交換し、時にはポジティブな対立があっても恐れません。一方、ぬるま湯組織では意味のある対立でも避け、積極的な意見交換が少なくなります。
また、心理的安全性の高い組織では業務や目的、成長への意識が高く、リスクをとって失敗から学ぶ姿勢があります。これに対し、ぬるま湯組織では失敗を恐れてリスクを取らず、現状維持に甘んじる傾向があります。
日本の企業はぬるま湯になりやすいと言われています。その理由として、「空気を読む」という言葉に代表される日本特有の企業風土が挙げられます。相手の顔色をうかがったり察したりするコミュニケーションが重視され、対立や衝突を避ける傾向にあります。そのため、表面的には人間関係が良好であっても、意欲が低く生産性の向上が見込めない、ぬるま湯組織が生まれやすいのです。
心理的安全性が注目される背景

グローバル化や技術革新の進展により、日本企業では多様な視点やアイデアを活かすことの重要性が増してきました。従来の日本的経営では集団主義や和を重んじる文化が強く、個人の意見表明が難しい面がありましたが、自由に意見が言いにくい組織文化という課題を解決し、イノベーションを生み出す手段として「心理的安全性」に注目が集まっています。
心理的安全性の重要性が広く認識されるようになったきっかけは、Google社の研究です。2012年から2015年にかけて実施された「プロジェクトアリストテレス」では、チームの生産性向上に必要な5つの要素が特定され、その中で最も重要なものが「心理的安全性」だったのです。さらに、心理的安全性の高いチームは生産性や創造性が向上することも明らかになりました。
この研究成果により、日本企業でも従業員一人ひとりが自由に意見を述べられる環境づくりが、生産性向上や創造性の促進、そして企業の競争力強化につながると認識されるようになったのです。
心理的安全性を構成する4つの要素

心理的安全性を構成する4つの要素として、話しやすさ、助け合い、挑戦、新奇歓迎があります。これらの要素をバランスよく高めることで、職場の心理的安全性を確保することが可能です。
構成要素 | 概要 | 該当する職場の特徴 |
|---|---|---|
話しやすさ | メンバーが自分の考えを安心して発言できる環境が整っている状態 |
|
助け合い | チームメンバーが互いにサポートし合い、協力して課題に取り組める関係性が確立されている状態 |
|
挑戦 | 新しい取り組みが奨励され、失敗も成長の過程として受け入れられる環境 |
|
新奇歓迎 | 多様な考え方を尊重し、従来の枠組みにとらわれない新しいアイデアを歓迎する風土 |
|
心理的安全性が低い職場で生じる4つの不安

心理的安全性が低い職場では、従業員は以下の4つの不安を抱えやすくなります。これらの不安は、個人のパフォーマンスを低下させ、組織全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・無知と思われる不安
上司や同僚に質問や相談をしたいときに、「そんなことも知らないのか」と思われるのではないかという不安から、必要な情報を得る機会を逃してしまい、業務の効率低下やミスの増加につながる可能性があります。
- ・無能と思われる不安
ミスや失敗を報告しなければならないとき、「こんな簡単な仕事もできないのか」と思われるのではないかという不安から、問題を隠蔽してしまい、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。
- ・邪魔をしていると思われる不安
「この場でこの話題を出すべきなのか」と悪い意味で空気を読みすぎることで、重要な意見や提案を控えてしまい、チームや組織におけるイノベーションの可能性を狭めてしまう恐れがあります。
- ・ネガティブと思われる不安
「自分の意見を言うことで、人の意見を否定していると思われるのではないか」という不安から、建設的な批判や異なる視点の提供を躊躇してしまい、チーム全体の問題解決能力や創造性の低下につながる可能性があります。
これらの不安は、従業員の自信を低下させ、本来の能力を発揮できない状況を生み出します。結果として、組織全体のパフォーマンスや革新性が損なわれる可能性があるのです。
心理的安全性が低すぎるとパワハラが起きやすい?

職場の心理的安全性が低いと、パワハラが発生しやすく、また解決も困難になります。このような職場には言いたいことが言えない雰囲気があるため、不快な言動に対して「やめてください」となかなか伝えられないでしょう。
パワハラ加害者の中には、自分の行動を単なる指導や教育と思い込んでいる人も多いです。周囲が何も言わなければ、加害者は自分の行動の問題に気づく機会を失い、結果としてパワハラが継続してしまいます。
「やめてと言ったら逆ギレされるのではないか」「どうせ言っても無駄」といった恐れや諦めが、問題をさらに悪化させます。対照的に、心理的安全性の高い職場では、気軽に意見を伝えられ、指摘された側も素直に受け止められるため、小さな問題が深刻なパワハラに発展する前に解決できるのです。
職場で心理的安全性を確保する6つのメリット

心理的安全性を職場で確保することは、組織全体に多くの利点をもたらします。心理的安全性を高めることで得られる6つの主要なメリットは以下になります。
- ・パフォーマンスが向上する
- ・会社への満足度が上がり離職率が下がる
- ・一人ひとりの責任感や積極性が向上する
- ・創造性が上がりイノベーションが起こりやすい
- ・問題の早期発見ができる
- ・DEIを促進させることができる
これらのメリットは、個人のパフォーマンス向上から組織の革新性強化まで、幅広い領域に及びます。以下では、それぞれについて解説します。
- パフォーマンスが向上する-
心理的安全性の高い職場では、従業員は人間関係にとらわれることなく、目の前の仕事に集中できます。「このような提案をしたら社内の人間関係を悪くするかもしれない」といった心理的な障壁を感じることなく、積極的に新しいアイデアを提案できるため、個人やチーム全体のパフォーマンスが向上します。
さらに、メンバー間で活発な情報共有が行われることで、それぞれの得意分野が明確になり、チーム全体の知識量も増加します。これらの要因が相まって、組織全体の生産性向上につながるのです。
- 会社への満足度が上がり離職率が下がる-
心理的安全性の高い職場環境では、従業員一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できていると実感できます。この実感が、仕事への満足度や組織への愛着心を高めます。結果として、従業員の会社に対するエンゲージメントが高まります。
エンゲージメントの向上は離職率の低下に直結し、優秀な人材の流出を防ぐことができます。このように、心理的安全性の確保は人材の定着率向上にも大きく貢献するのです。
- 一人ひとりの責任感や積極性が向上する-
心理的安全性が高い組織では、メンバーが自由に意見を述べたり、提案したりできる環境が整っています。自分の発言や意見が組織に受け入れられることで、個々の従業員は自身の役割や業務に対する関心度を高めていきます。
これにより、一人ひとりが責任感を持って仕事に向き合い、互いに切磋琢磨できる環境が自然と構築されていきます。結果として、組織全体の生産性と創造性が向上するのです。
- 創造性が上がりイノベーションが起こりやすい-
心理的安全性の高いチームでは、メンバー一人ひとりの個性や価値観が尊重されます。多様な価値観を持つメンバーが自由に意見を交換することで、さまざまな新しいアイデアが生まれやすくなります。また、失敗を恐れずに挑戦できる環境が整っているため、イノベーションが創出されやすくなります。
逆に、現場から出てきたアイデアを黙殺するような「現状維持」の姿勢を続けていると、組織の成長は望めません。心理的安全性の確保は、組織の創造性とイノベーション力を高める重要な要素なのです。
- 問題の早期発見ができる-
心理的安全性の高い職場では、「失敗したら非難されるかもしれない」という不安が軽減されます。その結果、ミスの隠蔽や報告の遅れといった問題が減少し、課題が表面化しやすくなります。業務を進める上でトラブルの発生は避けられませんが、早期に発見できれば被害を最小限に抑えることができます。
心理的安全性の確保は、問題の早期発見・早期対応を可能にし、組織のリスク管理能力を向上させる効果があるのです。
- DEIを促進させることができる-
DEIとは、「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」の頭文字を取った言葉で、多様な人材が公平に扱われ、互いに尊重し合える職場環境を指します。
心理的安全性の高い組織では、多様な価値観や背景を持つメンバーが安心して自己表現できる環境が整っています。これは、DEIの推進に不可欠な要素です。心理的安全性を確保することで、異なる視点や経験を持つ人々が積極的に意見を交わし、互いの違いを尊重しながら協働できるようになります。
結果として、組織全体でDEIが促進され、より創造的な職場環境が実現するのです。
職場の心理的安全性を評価する方法

職場の心理的安全性を評価する代表的な方法には、7つの質問と3つのサインというものがあります。ここでは、それぞれの評価方法についてわかりやすく説明していきます。
- 7つの質問 -
心理的安全性の概念を提唱したエドモンドソン教授は、組織やチームの心理的安全性に関する意識を評価するための7つの質問を開発しました。これらの質問は、チームメンバーがどの程度心理的安全性を感じているかを把握するのに役立ちます。
以下に、エドモンドソン教授が提案した7つの質問を紹介します。
【心理的安全性を測る7つの質問】
- 1.チーム内でミスをするとたいていの場合、非難される
- 2.チーム内では難しい問題や課題を互いに指摘し合える
- 3.チームメンバーの中に、異質な個性を理由に挙げて他者を拒絶する人がいる
- 4.チーム内でリスクの高い発言や行動をとっても安全だと感じられる
- 5.ほかのメンバーに助けを求めることは難しい
- 6.チーム内の誰もが、他者を意図的に陥れるような行動をしない
- 7.チームメンバーと働く際、自分のスキルや能力が尊重され、仕事に活かせていると感じられる
これらの質問に対し、ネガティブな回答が多いほど、そのチームや組織の心理的安全性は低いと考えられます。特に、質問1、3、5に対して「はい」という回答が多い場合、チーム内で信頼関係が築けておらず、メンバーが「無知」「無能」「邪魔」「ネガティブ」といった不安を抱えている可能性が高いといえます。
ただし、回答者は自分の期待値と照らし合わせて回答する傾向があるため、絶対的な評価指標としては扱えません。例えば、「はい、助けを求められます」と答えたとしても、それは回答者の「こうあるべきだ」という考えとの相対的な評価である可能性があります。
したがって、これらの質問から得られたデータは、マネージャーがチームの体験を振り返り、その体験を改善するために何を変えることができるかを前向きに考えるための材料として活用することが重要です。心理的安全性の向上は、単純なスコアリングではなく、継続的な対話と改善のプロセスを通じて達成されるものなのです。
- 3つのサイン -
心理的安全性を提唱したエドモンドソン教授は、7つの質問に加えて、より手軽に職場の心理的安全性を確認できる「3つのサイン」も提唱しています。
【心理的安全性の高いチームに見られる3つのサイン】
- ・ポジティブな言葉が飛び交っている:チームメンバーが「私たちはお互いを尊重している」「ありのままの自分でいられる」などの言葉を自然に口にしています。こうした発言は、チーム内に信頼関係が構築されている証拠です。
- ・失敗や問題についても話し合う:心理的安全性の高いチームでは、うまくいったことだけでなく、ミスや課題についても率直に議論します。
- ・職場に笑いとユーモアがある:心理的安全性の高い職場では、自然と笑顔や笑い声があふれています。緊張や不安を感じることなく自分らしくいられる環境では、ユーモアも生まれやすくなります。
チームリーダーは定期的にこれらのサインを意識し、心理的安全性の状態を把握することで、必要に応じて働きかけを行えます。
心理的安全性の高い職場の作り方

心理的安全性の高い職場を作るには、以下の方法があります。これらの方法を実践することで、従業員が自由に意見を述べ、創造性を発揮できる環境を整えることができるでしょう。
【心理的安全性の高い職場の作り方】
- ・従業員の意見の重要性についてしっかり教育する
- ・リーダーが自身の失敗を認め共有する
- ・積極的に意見を求める
- ・失敗やミスを肯定的に捉える
- 従業員の意見の重要性についてしっかり教育する-
従業員の意見の重要性について教育することは、心理的安全性を高める上で非常に効果的です。なぜなら、従業員一人ひとりが自分の意見や視点が組織にとって価値があると認識することで、積極的に発言するようになるからです。
具体的には、新入社員研修や定期的な全体会議の場で、経営陣が、従業員の意見がいかに重要であるかを明確に伝えるなどです。
例えば、「皆さんの日々の業務から得られる気づきや提案は、我が社の成長にとって不可欠です。どんな小さな意見でも、遠慮なく共有してください」といったメッセージを発信することで、従業員は自分の意見が歓迎されていると感じ、より積極的に発言するようになるでしょう。
- 自身の失敗を認めて共有する-
リーダーが自身の失敗を認め、それを共有することは、心理的安全性を高める上で非常に効果的です。これにより、失敗は恥じるべきものではなく、学びの機会として捉えるという組織文化が醸成されるからです。
例えば、部門長が月次会議で「先月の新規プロジェクトで私が判断ミスをしてしまい、納期に遅れが生じてしまいました。この経験から、今後はより慎重に計画を立てる必要があると学びました」と率直に語ることで、部下たちも自分の失敗を隠さずに共有しやすくなります。こうした姿勢が組織全体に浸透することで、失敗から学び、成長する文化が根付いていくのです。
- 積極的に意見を求める-
リーダーが積極的に意見を求めることは、心理的安全性を高める上でとても重要です。なぜなら、メンバーの意見を尊重し、それを求めていることを明確に示すことで、発言することへの心理的障壁を下げられるからです。
具体的には、会議の場で「この件について、皆さんはどう思いますか?」「他に考えられる方法はありますか?」といった質問を投げかけるのが効果的です。また、1対1のミーティングでも「あなたの視点から見て、この問題にはどのような解決策がありそうですか?」と積極的に部下の意見を引き出すことで、部下は自分の意見が重視されていると感じ、より自由に発言できるようになるでしょう。
- 失敗やミスを肯定的に捉える-
失敗やミスを肯定的に捉えることは、心理的安全性を高める上で重要な要素です。これにより、メンバーがリスクを恐れずに新しいアイデアを試したり、率直に問題を報告したりできる環境が整うからです。
例えば、新しい取り組みが失敗に終わった際に、リーダーが「失敗は成功の母です。この経験から何を学べるか、みんなで考えてみましょう」と前向きに対応することで、チームメンバーは失敗を恐れずにチャレンジする勇気を持つことができます。
また、ミスを報告した部下に対して「早期に気づいて報告してくれてありがとう。これで大きな問題になる前に対処できますね」と感謝の言葉をかけることで、問題の早期発見・報告を促進することができるでしょう。
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
心理的安全性の高い職場を実現することは、組織の成功と従業員の満足度向上に不可欠です。従業員が自由に意見を述べ、失敗を恐れずにチャレンジできる環境を整えることで、イノベーションが促進され、問題の早期発見・解決が可能になります。
リーダーは従業員の意見を積極的に求め、失敗を学びの機会として捉える姿勢を示すことが重要です。心理的安全性を高めることで、組織のパフォーマンスが向上し、離職率の低下やDEIの促進など、多くのメリットを享受できます。職場の心理的安全性を高める取り組みを始めることで、競争力のある組織づくりと従業員の成長を同時に実現できるでしょう。
TOPPANではコミュニケーション向上につながる、オフィスレイアウトのご提案が可能です。
心理的安全性を促進するコミュニケーションを重視したオフィスレイアウトをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください!
関連コラム

<TOPICS>オフィスコミュニケーションを活性化するには?レイアウトのコツや事例を紹介

<TOPICS>インフォーマルコミュニケーションとは?具体例やメリット・オフィスの事例