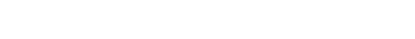<TOPICS>休憩室やリフレッシュスペースの設置もおすすめ!
従業員満足度(ES)とは|メリット・向上させる方法・最適な事例をご紹介

従業員満足度(ES)とは

従業員満足度(Employee Satisfaction/ES)は、企業における重要な指標の一つで、従業員が自身の仕事や職場環境にどの程度満足しているかを表します。具体的には、福利厚生、マネジメント、職場環境、働きがいなどの要素に対する従業員の満足度を総合的に評価したものです。
従業員満足度は、単に従業員の幸福度を測るだけでなく、組織の健全性や生産性を反映する指標でもあります。高い従業員満足度は、従業員のモチベーションや生産性の向上、顧客満足度の上昇、さらには企業の業績向上にもつながる可能性があります。
従業員満足度は、給与や福利厚生といった目に見える要素だけでなく、仕事のやりがい、キャリア成長の機会、職場の人間関係、企業文化への共感など、多岐にわたる要素から構成されています。そのため、従業員満足度を向上させるには、これらの多様な側面に対して総合的なアプローチが必要となります。
近年では、従業員満足度に加えて「従業員エンゲージメント」という概念も注目されています。エンゲージメントは、単なる満足度を超えて、従業員が組織に対してどれだけ愛着を持ち、積極的に貢献しようとしているかを表す指標です。従業員満足度とエンゲージメントを併せて考えることで、より包括的に従業員と組織の関係を理解し、改善することが可能となります。
従業員満足度を向上させることは、人材の定着率向上、優秀な人材の獲得、そして組織全体の活性化にもつながります。そのため、多くの企業が従業員満足度向上のためのさまざまな施策を実施し、定期的な調査を通じてその効果を測定しています。
従業員満足度を構成する要素

従業員満足度は複数の要素から成り立っており、これらの要素が総合的に評価されることで全体的な満足度が形成されます。各要素は従業員の仕事生活の異なる側面を反映しており、それぞれが重要な役割を果たしています。
以下の表で、主要な構成要素とその概要をまとめました。
要素 | 概要 |
|---|---|
企業理念・行動方針 | 会社の価値観や目標に対する従業員の共感度。理念への理解と実践が重要。 |
仕事内容 | 業務の質や量、やりがい、自己成長の機会に対する満足度。適材適所の人材配置が鍵。 |
マネジメント・評価 | 上司の指導力、公平な評価制度、フィードバックの質に関する満足度。 |
人間関係 | 同僚や上司との関係性、チームワーク、職場の雰囲気に対する満足度。 |
職場環境 | 物理的な作業環境、労働時間、ワークライフバランスに関する満足度。 |
給与 | 報酬の適切さ、昇給の機会、他社との比較における満足度。 |
福利厚生 | 各種手当、休暇制度、健康サポートなどの制度に対する満足度。 |
従業員満足度を高めるためには、これらの要素をバランス良く改善していく必要があります。特に重要なのは、単に表面的な対策を講じるのではなく、各要素の根本的な課題に取り組むことです。
例えば、企業理念の浸透を図るためには、単に掲示するだけでなく、日々の業務の中でその理念がどのように実践されているかを具体的に示すのが効果的です。
また、マネジメントや評価に関しては、公平性と透明性を確保しつつ、個々の従業員の成長を促進するような仕組みづくりが重要です。人間関係の改善には、オープンなコミュニケーションを促進し、チームビルディングを通じて相互理解を深める取り組みが有効でしょう。
給与や福利厚生については、従業員のニーズを的確に把握し、それに応じた柔軟な制度設計が求められます。同時に、これらの制度が従業員にとって本当に価値があるものかを定期的に見直すことも大切です。
従業員満足度の向上には、経営層から現場の従業員まで、組織全体で一丸となって取り組む姿勢が不可欠です。各要素に対して継続的な改善を行い、従業員の声に耳を傾けながら、働きやすい環境づくりを進めていくことが、従業員満足度の向上につながるのです。
従業員満足度を調査する方法

従業員満足度を正確に把握し、効果的な改善策を講じるためには、適切な調査方法を選択して実施することが不可欠です。主な調査方法としては、アンケート調査と面接調査が広く用いられています。
アンケート調査は、多数の従業員から短時間で幅広い意見を収集できる利点があります。オンラインツールを活用することで、匿名性を確保しつつ、効率的にデータを集計・分析することが可能です。質問項目は、職場環境、仕事内容、人間関係、評価制度など、多岐にわたる要素をカバーし、数値評価と自由記述を組み合わせることで、より詳細な実態把握ができます。
一方、面接調査は、従業員の生の声や非言語的な反応を直接観察できる利点があります。特定の課題について深掘りした情報を得たい場合や、アンケート調査では表面化しにくい潜在的な問題を探る際に有効です。
ただし、時間と人的リソースを要するため、従業員数の多い企業では全従業員を対象とするのは現実的ではありません。そのため、部署や役職などの属性を考慮してサンプリングを行い、代表性のある意見を収集することが重要です。
多くの企業では、アンケート調査と面接調査を組み合わせて実施することで量的データと質的データの両方を収集し、より包括的な分析を行っています。
従業員満足度調査を進める手順は、以下の通りです。
【従業員満足度を調査する手順】
- 1.調査の目的と範囲を明確化する
- 2.調査方法(アンケート・面接)を選択し、質問項目を設計する
- 3.調査の実施時期と期間を決定し、従業員に事前周知を行う
- 4.匿名性と回答の秘密保持を確保した上で調査を実施する
- 5.収集したデータを集計・分析し、課題や傾向を抽出する
- 6.分析結果に基づいて改善策を検討・立案する
- 7.調査結果と改善計画を従業員にフィードバックする
- 8.改善策を実行し、その効果を定期的にモニタリングする
調査を実施する際は、従業員が率直な意見を表明できるよう、匿名性の確保や回答内容の秘密保持に十分配慮することが重要です。また、調査結果を単なるデータとして扱うのではなく、具体的な改善アクションにつなげることで、従業員の信頼を獲得し、次回の調査への協力姿勢を高めることができます。
定期的な調査の実施と、それに基づく継続的な改善活動を通じて、従業員満足度の向上と組織の活性化を図ることが企業の業績アップにもつながるのです。
従業員満足度調査時の注意点

従業員満足度調査を実施する際には、正確かつ有意義な結果を得るために、いくつかの注意点があります。これらの点に留意することで、調査の信頼性と有効性を高め、得られた情報を組織改善に効果的に活用することができます。
以下は、主な注意点になります。
- ・調査の目的を明確にし、事前に従業員に周知する
- ・回答者の匿名性を確実に担保する
- ・質問項目は適切な数に絞り、回答の負担を軽減する
- ・「満足ですか?」という直接的な質問だけでなく、具体的な状況や行動に関する質問も含める
- ・文化的背景を考慮し、日本特有の遠慮がちな回答傾向に注意する
- ・平均点だけでなく、回答の分布や相関関係も分析する
- ・従業員にとって重要度の高い項目を特定し、優先順位をつける
- ・調査結果を速やかにフィードバックし、改善アクションを示す
これらの注意点を踏まえることで、より実態に即した調査結果を得ることができます。特に、日本の組織文化では直接的な批判を避ける傾向があるため、「大変不満」という回答が得られにくい可能性があります。そのため、質問の仕方や回答の解釈には細心の注意が必要です。
また、単に満足度の高低を測るだけでなく、各項目が従業員にとってどの程度重要かを把握することも重要です。例えば、福利厚生の満足度が低くても、それが従業員にとって重要度の低い項目であれば、改善の優先順位は下がるかもしれません。
さらに、調査結果の分析では平均点だけでなく、回答の分布や他の要因との相関関係を見ることで、より深い洞察が得られます。例えば、給与満足度と業績の関係や、マネジメント満足度と離職率の関連性など、多角的な分析を行うことで、より効果的な改善策を導き出すことができます。
そして、調査結果を従業員にフィードバックし、具体的な改善計画を示すことが重要です。これにより、従業員の信頼を獲得し、次回の調査への協力度を高めることができます。同時に、改善アクションの進捗を定期的に報告することで、組織が変革に向けて動いていることが従業員にしっかりと伝わるでしょう。
従業員満足度の向上によって得られるメリット

従業員満足度の向上は、企業にとってたくさんのメリットをもたらします。単に従業員の幸福度を高めるだけでなく、企業全体の業績や競争力の向上にも直結します。
主なメリットは以下の通りです。
【従業員満足度の向上によって得られるメリット】
- ・生産性の向上
- ・人材流出の防止・人材の定着率向上
- ・顧客満足度(CS)の向上
- ・企業イメージの向上・ブランディング
これらのメリットは相互に関連し合い、好循環を生み出します。例えば、生産性の向上は顧客満足度の向上につながり、それが企業イメージの向上をもたらします。さらに、良好な企業イメージは優秀な人材の獲得と定着を促進し、結果としてさらなる生産性向上につながるのです。
以降では、それぞれのメリットについて解説します。
- 生産性の向上 -
従業員満足度の向上は、直接的に企業の生産性向上につながります。満足度の高い従業員は、仕事に対する意欲が高く、自発的かつ創造的に業務に取り組む傾向があります。従業員満足度が向上することで業務効率が上がり、より質の高い成果を生み出すことができるでしょう。
例えば、ある製造業の企業では、従業員満足度向上プログラムを導入した結果、1年後に生産効率が15%向上したという事例があります。従業員が自身の仕事に誇りを持ち、職場環境に満足していることで、無駄な作業時間が減少し、創意工夫の意識が高まったのです。
また、満足度の高い従業員は、チームワークやコミュニケーションにも積極的になります。これにより、部門間の連携がスムーズになり、プロジェクトの進行速度が上がるとともに、イノベーションが生まれやすい環境が整います。結果として、企業全体の競争力が高まり、市場での優位性を確立することができるのです。
- 人材流出の防止・人材の定着率向上 -
従業員満足度が高い企業では、人材の定着率が著しく向上します。従業員が自社に対して強い帰属意識を持ち、仕事にやりがいを感じていれば、転職を考える可能性は大幅に低下します。これは、企業にとって非常に大きなメリットです。
具体的な例を挙げると、ある IT 企業では従業員満足度向上施策を実施した結果、年間の離職率が25%から8%に減少しました。これにより、採用コストや新人教育にかかる費用が大幅に削減され、さらに経験豊富な従業員が長期的に働き続けることで、企業の知識やノウハウの蓄積が進みました。
また、人材の定着率が高いことは、企業の安定性や信頼性の指標としても機能します。取引先や顧客にとっても、従業員が長く働き続ける企業は信頼できるパートナーとして認識されやすくなります。さらに、社内での人間関係や信頼関係が深まることで、より効率的な業務遂行や革新的なアイデアの創出にもつながるのです。
- 顧客満足度(CS)の向上 -
従業員満足度の向上は、顧客満足度(CS)の向上に直接的な影響を与えます。満足度の高い従業員は、自社の商品やサービスに対する理解が深く、顧客に対してより親身で質の高い対応を行う傾向があります。これにより、顧客との信頼関係が構築され、顧客満足度が向上するのです。
例えば、ある小売チェーンでは、従業員満足度向上プログラムを実施した結果、顧客満足度調査のスコアが半年で20%上昇しました。従業員が自社の理念や商品に誇りを持ち、積極的に顧客とコミュニケーションを取ることで、顧客のニーズをより深く理解し、適切な提案ができるようになったのです。
さらに、満足度の高い従業員は、顧客の声を積極的に社内にフィードバックする傾向があります。これにより、商品やサービスの改善が迅速に行われ、結果として顧客満足度がさらに向上するという好循環が生まれます。顧客満足度の向上は、リピート率の上昇やクチコミによる新規顧客の獲得にもつながり、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。
- 企業イメージの向上・ブランディング -
従業員満足度の高さは、企業イメージの向上とブランディングに大きく貢献します。従業員が自社に対して良い印象を持ち、誇りを感じていれば、それは自然と外部に伝わり、企業の評判を高めることにつながります。
具体例として、ある大手テクノロジー企業では、従業員満足度向上への取り組みを積極的に行った結果、「働きたい企業ランキング」で3年連続トップ10入りを果たしました。これにより、優秀な人材の応募が増加し、採用における競争力が大幅に向上しました。
また、従業員満足度の高さは、社会的責任(CSR)の観点からも企業の評価を高めます。従業員を大切にする企業は社会からも信頼され、持続可能な事業運営を行っているという印象を与えます。これは、投資家や取引先との関係構築にも良い影響を与え、企業の成長機会を拡大させます。
さらに、満足度の高い従業員は、自社の商品やサービスを自信を持って他者に勧めるため、口コミマーケティングの効果も期待できます。このような自然な形での宣伝活動は、消費者にとって信頼性が高く、企業ブランドの価値向上に大きく寄与するのです。
従業員満足度を向上させる方法

従業員満足度を向上させるには、組織全体で多角的なアプローチが必要です。主な方法として、以下が挙げられます。
【従業員満足度を向上させる方法】
- 経営理念の共有
- 適切な部署への配置
- 快適な職場環境への改善
- 業務負担の偏りの改善
- 評価制度の見直し
- 福利厚生の充実
- 従業員同士のコミュニケーションの活性化
以下では、各方法について解説していきます。
- 経営理念の共有 -
経営理念の共有は、従業員と組織の価値観を一致させ、強い一体感を醸成する上で非常に重要です。具体的には、定期的な全社集会での経営陣による理念の説明や、日々の業務と理念のつながりを示す具体例の共有が効果的です。また、理念を体現した従業員を表彰する制度を導入したり、社内報やイントラネットで理念関連のコンテンツを発信したりすることも有効です。
例えば、あるIT企業では、毎月のチームミーティングで、その月の業務が会社のビジョンにどう貢献したかを共有する時間を設けています。これにより、従業員は自分の仕事の意義を再確認し、モチベーションの向上に寄与しています。
経営理念が従業員に深く浸透すれば、個々の判断や行動の指針となり、自律的な業務遂行が可能になります。結果として、従業員のエンゲージメントが高まり、従業員満足度の向上に大きく寄与するのです。
- 適切な部署への配置 -
従業員の適性や能力に合った部署への配置は、従業員満足度を高める上で非常に重要です。これを実現するためには、定期的なスキル評価と適性診断の実施、キャリア面談の実施、社内公募制度の活用などが効果的です。
例えば、ある製造業の企業では、年2回のキャリア面談を通じて従業員の希望や適性を把握し、それに基づいて適切な部署への異動を行っています。その結果、従業員の職務満足度が20%向上し、生産性もアップしました。
適材適所の人員配置は、従業員個人の成長を促すだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。自分の強みを活かせる環境で働くことで、従業員は高いモチベーションを維持し、より良い成果を出すことができるのです。
- 快適な職場環境への改善 -
快適な職場環境は、従業員の生産性と満足度を直接的に高めます。具体的には、オフィスレイアウトの最適化、最新のIT機器や業務支援ツールの導入、休憩スペースの充実、フレックスタイム制やテレワークの導入などが効果的です。
例えば、ある広告代理店では、創造性を促進するためにオフィス内にブレインストーミング専用のスペースを設置しました。また、集中作業が必要な時に利用できる静かな個室も用意しました。これらの施策により、従業員の業務効率が向上し、残業時間が平均20%削減されました。
快適な職場環境は、単に物理的な快適さだけでなく、働き方の柔軟性も含みます。テレワークやフレックスタイム制の導入により、ワークライフバランスが改善され、結果として従業員満足度の向上につながるのです。
- 業務負担の偏りの改善 -
業務負担の偏りは、従業員の不満や疲弊の主要因となるため、その改善は従業員満足度の向上に直結します。具体的には、定期的な業務量調査の実施、タスク管理ツールの導入による業務の可視化、チーム内でのタスクローテーションの実施、業務プロセスの見直しと効率化などが効果的です。
例えば、ある金融機関では、各部署の業務量を可視化するシステムを導入しました。これにより、特定の部署や個人に業務が集中している状況が明らかになり、適切な人員配置や業務の再分配が可能になりました。結果として、従業員の残業時間が30%減少し、ストレスレベルも大幅に低下しました。
業務負担の適正化は、従業員の健康維持やワークライフバランスの改善にも寄与します。さらに、余裕が生まれることで創造的な業務への取り組みも可能になり、組織全体の生産性向上にもつながるのです。
- 評価制度の見直し -
公正で透明性の高い評価制度は、従業員の信頼感とモチベーション向上に不可欠です。従業員満足度を高めるための評価制度の見直しには、明確な評価基準の設定と公開、定期的なフィードバック面談の実施、360度評価の導入、評価結果に基づく具体的な成長支援プランの策定などが効果的です。
例えば、ある企業では、四半期ごとの目標設定と進捗確認を行い、上司と部下が定期的に対話する機会を設けています。また、年に一度の評価では、同僚や部下からのフィードバックも含めた360度評価を導入しました。これにより、評価の公平性が高まり、従業員の評価制度への信頼度が40%向上しました。
適切な評価制度は、従業員の努力を正当に認識し、適切な報酬や成長機会につなげることができます。これにより、従業員は自身の貢献が組織に認められていると実感し、より高いモチベーションで業務に取り組むようになるのです。
- 福利厚生の充実 -
充実した福利厚生は、従業員の生活の質を向上させ、仕事への満足度を高める重要な要素です。従業員満足度の向上に効果的な福利厚生としては、柔軟な休暇制度、健康支援プログラム、育児・介護支援、自己啓発支援などが挙げられます。
例えば、ある製造業の企業では、従業員の健康増進を目的としたウェルネスプログラムを導入しました。健康診断の結果に基づいた個別の健康改善プランの提供や、社内でのヨガクラスの開催などを行った結果、従業員の欠勤率が20%減少し、業務効率も向上しました。
福利厚生の充実は、従業員の生活面でのサポートを通じて、会社に対する安心感や信頼感を高めます。これにより、従業員は仕事により集中でき、長期的なキャリアプランを描くことができるようになるのです。
- 従業員同士のコミュニケーションの活性化 -
活発なコミュニケーションは、職場の雰囲気を良好に保ち、チームワークを向上させる重要な要素です。従業員同士のコミュニケーションを活性化させるための具体的な方法としては、定期的な社内イベントの開催、オープンスペースやコラボレーションエリアの設置、社内SNSやチャットツールの導入、メンター制度の導入などが挙げられます。
例えば、あるIT企業では、月に一度「アイデアソン」と呼ばれる部署横断的なブレインストーミングイベントを開催しています。これにより、普段接点の少ない部署間でのコミュニケーションが活性化され、新しいプロジェクトのアイデアが生まれるなど、イノベーションの促進にもつながっています。
活発なコミュニケーションは、情報共有の円滑化や相互理解の促進につながり、職場の一体感を高めます。また、困ったときに気軽に相談できる環境が整うことで、問題解決のスピードが上がり、ストレスの軽減にもつながります。結果として、従業員の帰属意識が高まり、従業員満足度の向上に大きく貢献するのです。
従業員満足度の向上には休憩室・リフレッシュスペースの設置がおすすめ!
従業員満足度を向上させる方法の一つとして、休憩室やリフレッシュスペースの設置が非常に効果的です。こうしたスペースを設けることで、従業員がリラックスしたり、気分転換を図ったりする機会が増え、ストレス軽減やモチベーション向上につながります。また、同僚との casual なコミュニケーションの場としても機能し、部門を超えた情報交換や新たなアイデアの創出にも寄与します。
休憩室やリフレッシュスペースの設置は、単に従業員の休憩時間を確保するだけでなく、会社が従業員の well-being を重視していることを示すシグナルにもなります。これにより、従業員の会社に対する信頼感や帰属意識が高まり、結果として生産性の向上にもつながるのです。
このような取り組みの具体例として、株式会社文昌堂のオフィス改修事例を紹介します。
- 株式会社文昌堂 -

株式会社文昌堂様は、東京都台東区に本社を置く企業です。2024年3月に完了したオフィス改修プロジェクトでは、従業員満足度の向上を主要な目的の一つとして、7階と8階の計260坪(860㎡)にわたる大規模な改修を実施しました。
この改修では、「安心感・居心地の良さと新しさをMIXさせたオフィス空間」をテーマに掲げ、従来の風通しの良い企業風土を維持しつつ、新たな要素を取り入れることで、従業員の満足度向上を目指しました。
特筆すべきは、7階に設けられた「リフレッシュ・フォーカスエリア」です。このエリアは、ランチタイムやコーヒーブレイクなど、従業員が自由にリラックスできるスペースとして設計されています。くつろぎの空間を提供するだけでなく、壁際にはハイカウンターを設置し、一人で集中して作業を行いたい時にも利用できるよう工夫されています。
このようなマルチファンクショナルな空間設計により、従業員は気分や業務の状況に応じて柔軟に場所を選択できるようになりました。ちょっとした休憩から集中作業まで、多様なニーズに対応できる環境を整えることで、従業員の快適性と生産性の両立を図っています。
株式会社文昌堂様の事例は、リフレッシュスペースの設置が単なる休憩場所の提供にとどまらず、従業員の働き方全体を変革し、満足度を向上させる重要な要素となりうることを示しています。適切に設計された休憩室やリフレッシュスペースは、従業員の心身のリフレッシュを促すだけでなく、創造性の向上やチームワークの強化にも貢献し、結果として組織全体の生産性向上につながるのです。
関連記事:株式会社文昌堂 様 オフィス改修
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
従業員満足度は、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素です。ES向上に取り組むことで、生産性の向上、人材の定着率アップ、顧客満足度の向上、企業イメージの向上など、多様なメリットが得られます。経営理念の共有や適切な人材配置、快適な職場環境の整備、評価制度の見直しなど、さまざまな施策を通じてESを高めることが可能です。
特に、休憩室やリフレッシュスペースの設置は、従業員の心身のリフレッシュとコミュニケーション促進に効果的です。ESの向上に継続的に取り組むことで、企業の成長と従業員の幸福度向上の好循環を生み出すことができるでしょう。
TOPPANではコミュニケーション向上につながる、オフィスレイアウトのご提案が可能です。
チームビルディングを促進するコミュニケーションを重視したオフィスレイアウトをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください!
関連コラム

<TOPICS>オフィスのリフレッシュスペースとは|必要性やポイント、事例を紹介

<TOPICS>社内コミュニケーションを活性化させるアイデア|メリットと事例を紹介