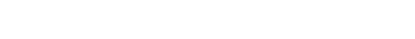<TOPICS>定期的なアップデートが万全な体制のカギ!
オフィス防災は必須!オフィスの防災対策の基本やオフィス改修事例を紹介

企業のオフィス防災の重要性

オフィス防災とは、火災や地震などの自然災害から建物や従業員を守ることです。企業にとってオフィス防災は、従業員の安全を確保するだけでなく、被災後の事業継続を図る上でも必要不可欠です。
労働契約法第5条では、企業は従業員の命や身体の安全確保に努める「安全配慮義務」があると定められています。オフィス防災を怠り、災害時に従業員に被害が出た場合、安全配慮義務違反として企業の法的責任が問われる可能性があります。
さらに、新型コロナウイルスの流行により、働き方が大きく変わりました。テレワークの浸透で、オフィスだけでなく自宅やサテライトオフィスなど働く場所が多様化しています。このような状況下で災害が起きた場合、防災担当者がオフィスに不在の可能性もあり、その際はオフィスに居合わせた従業員だけで対応する必要があります。
したがって企業は、日頃から全従業員にオフィス防災の内容を周知徹底し、防災担当者が不在でも迅速に行動できる体制づくりが求められます。備蓄品の保管場所を分散したり、個人用の防災セットを事前配布したりするなど、感染症対策も考慮した新しい防災対策が必要です。
コロナ禍を機に、企業のオフィス防災は「防災担当者任せ」から「全従業員参加型」へとシフトしつつあります。テレワーク中も含めた全従業員の安全確保と、事業継続のために、オフィス防災の重要性はますます高まっているのです。
オフィスの基本的な防災対策

オフィスで災害が発生した際、人的・物的被害を最小限に抑えるためには、日頃からの防災対策が欠かせません。ここでは、オフィスにおける基本的な防災対策として、以下の項目について説明します。
- ・インフラ停止時のための備蓄
- ・防災グッズの用意
- ・感染症対策の準備
- ・従業員全員の連絡体制の確保
- ・避難経路・ハザードマップの確認
- ・防災マニュアルの作成・周知
- ・動線を作るためのオフィスレイアウト
- ・業務上で重要なデータのバックアップ
- ・避難訓練の定期的な実施
これらの対策を万全にしておくことで、いざという時に従業員の安全を確保し、事業の早期復旧につなげることができます。
それでは、各項目について詳しく見ていきましょう。
- インフラ停止時のための備蓄 -
大規模災害が発生すると、水道、ガス、電気などのライフラインが停止し、復旧までに数日かかることがあります。そのため、最低3日分、できれば1週間分の備蓄を確保しておくことが重要です。
インフラ停止時のための主な備蓄品は以下の通りです。
- ・飲料水(1人1日3リットルが目安)
- ・非常食(アルファ米、乾パン、缶詰など)
- ・簡易トイレ、トイレットペーパー
- ・毛布、寝袋、断熱シート
- ・マスク、消毒液、ウェットティッシュ
- ・ラジオ、懐中電灯、電池
- ・救急セット(ばんそうこう、包帯、消毒薬など)
備蓄品は定期的に賞味期限をチェックし、古いものから使用・交換するようにしましょう。また、備蓄場所は全従業員に周知し、誰でもすぐに取り出せる状態にしておくことが大切です。
- 防災グッズの用意 -
災害時、従業員の安全を確保するためには、適切な防災グッズを準備しておく必要があります。オフィスに備えるべき主な防災グッズは以下の通りです。
- ・ヘルメット、防災ずきん
- ・防災頭巾、防煙マスク
- ・軍手、ロープ、スコップ
- ・消火器、消火砂、バケツ
- ・非常用発電機、投光器
- ・クラッシュハンマー、バール
- ・拡声器、トランシーバー
- ・地図、コンパス、ラジオ
防災グッズは全従業員が使用方法を理解し、いざという時に迅速に扱えるようにしておきましょう。
また、グッズの定期点検を欠かさず、不具合があれば速やかに修理・交換します。
- 感染症対策の準備 -
新型コロナウイルスの流行により、防災備蓄品の中にも感染症対策アイテムが欠かせなくなりました。
主な感染症対策グッズは以下の通りです。
- ・マスク
- ・消毒液
- ・非接触型体温計
- ・ゴム手袋
- ・パーティション
感染症の拡大を防ぐには、これらのグッズを十分に備蓄するとともに、正しい使用方法を従業員に周知することが重要です。また、オフィスの換気や消毒、三密の回避など、日頃からの感染予防対策も欠かせません。
- 従業員全員の連絡体制の確保 -
災害時には従業員の安否確認を迅速に行い、的確な指示を出す必要があります。そのためには、日頃から従業員全員の連絡体制を整えておくことが重要です。
具体的には、緊急連絡網の作成と定期的な更新、安否確認システムの導入、連絡手段の複数化(電話、メール、SNSなど)などが挙げられます。連絡先には、従業員本人だけでなく家族の連絡先も含めておくと良いでしょう。
また、テレワーク中の従業員も含めた全員参加の安否報告訓練を定期的に実施し、連絡体制の実効性を確認しておくことが大切です。
- 避難経路・ハザードマップの確認 -
オフィスの立地や周辺環境によって、想定される災害やリスクは異なります。建物内の避難経路や、自治体のハザードマップを確認し、災害ごとの適切な避難行動を従業員全員で共有しておく必要があります。
避難経路については、非常口や階段の位置を掲示し、机の配置などで通路をふさがないよう日頃から配慮が必要です。また、ハザードマップで浸水想定区域や土砂災害警戒区域を把握し、垂直避難の必要性なども確認しておきます。
これらの情報は防災訓練の際に活用し、避難場所や経路を従業員が体感できるようにすることが大切です。
- 防災マニュアルの作成・周知 -
オフィスの防災対策を実効性のあるものにするには、防災マニュアルの整備が欠かせません。防災マニュアルには、災害発生時の対応手順、役割分担、連絡先などを具体的に記載します。
マニュアル作成の際は、様々な災害を想定し、テレワーク中の従業員への対応も含めて検討することが重要です。作成後は、全従業員への配布と読み合わせを行い、定期的な見直しも忘れずに行います。
また、防災マニュアルを形骸化させないためには、日頃の防災教育や訓練が大切です。マニュアルの内容を実践的に習得できるよう、工夫を凝らしたプログラムを企画しましょう。
- 動線を作るためのオフィスレイアウト -
災害時の避難をスムーズに行うには、日頃からオフィスレイアウトに工夫が必要です。非常口や避難経路に物を置かない、机の配置で適切な幅員を確保するなど、安全に避難できる動線づくりが重要です。
また、キャビネットや家具は壁に固定し、収納庫は施錠できるものを選ぶなど、転倒や散乱防止対策も施しておきます。ガラス飛散防止フィルムを貼るのもお勧めです。
レイアウト変更の際は、防災の視点を盛り込み、従業員の安全確保を最優先に考えることが大切です。
- 業務上で重要なデータのバックアップ -
災害により、パソコンやサーバーが損傷を受けると、業務の継続が難しくなります。重要なデータを失わないためにも、日頃からバックアップを取っておくことが重要です。
クラウドストレージの活用や、外付けハードディスクへの定期的な保存など、方法は様々です。自動バックアップ機能を利用し、人的ミスを防ぐのも有効でしょう。
バックアップ作業は、できるだけ差分バックアップで行い、世代管理も意識します。また、バックアップデータ自体の保管場所にも注意が必要です。オフィスとは別の遠隔地に保管できれば理想的です。
- 避難訓練の定期的な実施 -
オフィスの防災力を高めるには、避難訓練の実施が欠かせません。年1回の実施が義務付けられていますが、企業の規模や業態に合わせ、より頻繁に行うことをお勧めします。
訓練では、従業員の安否確認、避難経路の確認、消火器の使用方法など、基本的な動きを確実に身につけることが重要です。また、シナリオを毎回変更し、様々な状況を想定した訓練を心がけましょう。
訓練の実施にあたっては、テレワーク中の従業員も参加できる仕組みづくりが必要です。Web会議システムを活用した参加など、新しい発想で取り組んでみてください。
オフィス防災は定期的な見直しが大切

オフィス防災対策は、一度策定したら終わりではありません。社会情勢の変化や新たなリスクの出現に合わせ、定期的に内容を見直し、アップデートしていく必要があります。
例えば、新型コロナウイルスの流行により、オフィスの防災備蓄品に感染症対策アイテムが加わりました。また、テレワークの普及で、防災体制もオフィスに居る従業員だけでなく、在宅勤務者も含めた対応が求められるようになりました。
防災対策の見直し頻度としては、最低でも年1回は行うことが望ましいでしょう。ただし、大規模な自然災害の発生や、世の中の大きな変化があった場合は、臨時で見直しを行う必要があります。
見直しの際は、以下のような点をチェックしましょう。
- ・防災マニュアルの内容が最新の状況に合っているか
- ・備蓄品の賞味期限や数量は適切か
- ・防災グッズに不具合はないか
- ・連絡網は最新の情報に更新されているか
- ・避難経路に変更はないか
これらの点検とともに、従業員の防災意識を高めるための教育や啓発活動も重要です。防災訓練の内容を工夫したり、講演会を開催したりするなど、継続的な取り組みが求められます。
また、オフィスの防災グッズを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- ・災害の種類に応じた適切なアイテムを揃える
- ・全従業員分の数量を確保する
- ・使用方法がシンプルで、誰でも扱えるものを選ぶ
- ・定期的なメンテナンスが必要なものは避ける
- ・備蓄スペースを考慮し、コンパクトなものを選ぶ
オフィス防災は、従業員の安全を守り、事業を継続するための重要な取り組みです。定期的な見直しを行い、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことで、より実効性の高い防災体制を築いていきましょう。
オフィス見学のご案内

最新のオフィスを見学してみたい方必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!
TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。
より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!
まとめ
オフィス防災は、企業にとって従業員の安全確保と事業継続のために欠かせない取り組みです。備蓄品や防災グッズの準備、感染症対策、連絡体制の確保など、日頃からの備えが重要です。また、オフィスレイアウトの工夫や避難訓練の実施、定期的な見直しも必要不可欠です。オフィス防災対策を万全にすることで、いざという時に従業員の命を守り、早期の業務復旧を実現できます。企業の存続と発展のために、オフィス防災への積極的な取り組みが求められています。
TOPPANではオフィスの改修・リニューアルはもちろんのこと、オフィスの環境整備に関するご相談も承っております。検討中の方はぜひ、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください!
関連コラム

<TOPICS>オフィス環境改善の取り組み例7選|おすすめのグッズや事例も紹介

<TOPICS>BCP対策とは?オフィスでの策定方法や運用のコツを解説