
「和室を洋風の雰囲気に変えたい」「畳の上でも椅子やキャスター付きの家具を使いたい」と思ったことはありませんか?
近年、畳の上にフローリング材を敷いて手軽に部屋のイメージチェンジを楽しむ方が増えています。
しかし対策せずにフローリング材を敷いてしまうと、カビやダニが発生したり、賃貸住宅の場合は原状回復が難しくなったりするリスクがあり注意が必要です。
この記事では、畳の上にフローリングを敷く正しい方法や注意点、カビを防ぐポイントを詳しく紹介します。さらに、長く快適に使うためのリフォーム手段や費用相場も解説します。
和室を手軽に洋室化したい方は、ぜひ参考にしてください。
TOPPAN(東証プライム上場)が運営する「リフォトル」では、国土交通省 登録団体に所属する優良リフォーム会社を無料で紹介しています。ぜひお気軽にお申し込みください。
国土交通省登録団体に所属する優良リフォーム会社をご紹介!
畳の上にフローリングを敷いても大丈夫?その方法は?

畳の上にフローリングを敷くことは可能です。実際、畳をはがさずにDIYで洋室のような雰囲気へ変える方法はいくつもあります。
ただし、畳の状態や湿気対策を無視すると、カビや沈み込みの原因になります。つまり、「できるけれど注意が必要」というのが正確な答えです。
ここでは、畳を残したままフローリング化する方法とポイント、商品タイプごとの特徴をまとめて紹介します。
畳の上にそのまま敷く方法とポイント
畳をはがさずにフローリング化する場合は、「置くだけ」で使えるタイプがおもな選択肢になります。
接着剤や釘を使わず、畳の上にフローリング(またはフローリング調のパネルなど)を並べるだけの簡単施工が魅力です。特別な道具や知識も不要で、DIY初心者の方でもチャレンジしやすい方法といえます。
ただし、畳の上に直接フローリングを敷く場合、以下の点に注意しましょう。
- 畳の状態確認
畳が傷んでいたり、湿気を含んでいるとカビやダニのリスクが高まります。事前に畳の状態をしっかりチェックし、必要に応じて乾燥やクリーニングをしてください。
- 床材の選定
裏面に滑り止め加工があるものや、通気性を考慮したものを選ぶと安心して使えます。
- 段差対策
フローリングを敷くことで、部屋の出入口に段差が生じることがあります。転倒防止やつまずき対策として、段差解消スロープなどを利用しましょう。
「畳の上にフローリング」で、よく使われる商品タイプ
畳の上に敷けるフローリング材にはいくつかの種類があります。フローリングそのものの厚みや施工方法の違いによって、仕上がりや歩き心地も変わります。
以下に、おもなタイプと特徴をまとめました。
| タイプ | 特徴・メリット | 注意点 |
| フローリング (約12mm厚・木質) |
・木質の上質感がある。 ・耐久性が高く安定した踏み心地。 ・価格はやや高めだが長期使用向き。 |
通常は釘や接着剤を使って固定するため、置くだけだと凸凹やズレが生じやすい。 |
| 薄型フローリング (約3〜6mm厚・木質) |
・軽量で扱いやすく重ね張り向け。 ・段差を抑えられDIYにも使いやすい。 ・価格は中程度でコスパが良い。 |
硬い下地に接着剤で張る想定のため、畳上だと割れやはがれが生じやすい。 |
| フロアタイル (2.5mm厚・塩ビ) |
・木目調デザインが豊富でDIYに人気。 ・水や汚れに強く部分交換も可能。 ・価格は比較的安い。 |
塩ビ素材のため通気性がなく、湿気が溜まりやすい。 1枚が小さいため、ズレ防止が必要。 |
| ウッドカーペット (約5〜7mm厚・木質) |
・広範囲を覆え短時間で洋室風に。 ・価格は中〜高程度でデザイン性重視向き。 |
6畳程度で20~30kg程度の重量がある。 切り欠きには工具が必要。 |
| クッションフロア (約2mm厚・塩ビ) |
・やわらかな踏み心地。 ・汚れを拭き取りやすくメンテナンス性が高い。 ・価格も安め。 |
塩ビ素材のため湿気が溜まりやすい。 薄いためつなぎ目や端がめくれやすい。 |
短期間の模様替えなら、フロアタイルやクッションフロアでも十分対応できます。ただし、長く使うなら、木質のフローリングなど耐久性のある素材を選ぶと安心して使えます。
デザインだけでなく、使う期間や生活スタイルも考えながら選んでみてくださいね。
賃貸でも使える?原状回復の可否
賃貸でも畳の上にフローリングを敷くことは可能ですが、「原状回復できるかどうか」が最も重要なポイントになります。
一般的なフローリング材は硬く、畳の表面が押しつぶされたり、跡が残ったりするおそれがあります。そのため、やわらかさのあるフロアタイルやクッションフロアなどの素材を選ぶと安心です。
こうしたタイプは軽くて扱いやすく、退去時も簡単に取り外せます。見た目を変えたいときや短期間の模様替えにもおすすめです。
ただし、塩ビ素材のため通気性がなく、湿気がこもるとカビや変色の原因になることがあります。敷く前には防カビシートなどを使い、定期的にめくって風を通すようにしましょう。
キズ・湿気対策を怠らなければ、賃貸でも安心してフローリング風の空間を楽しめます。
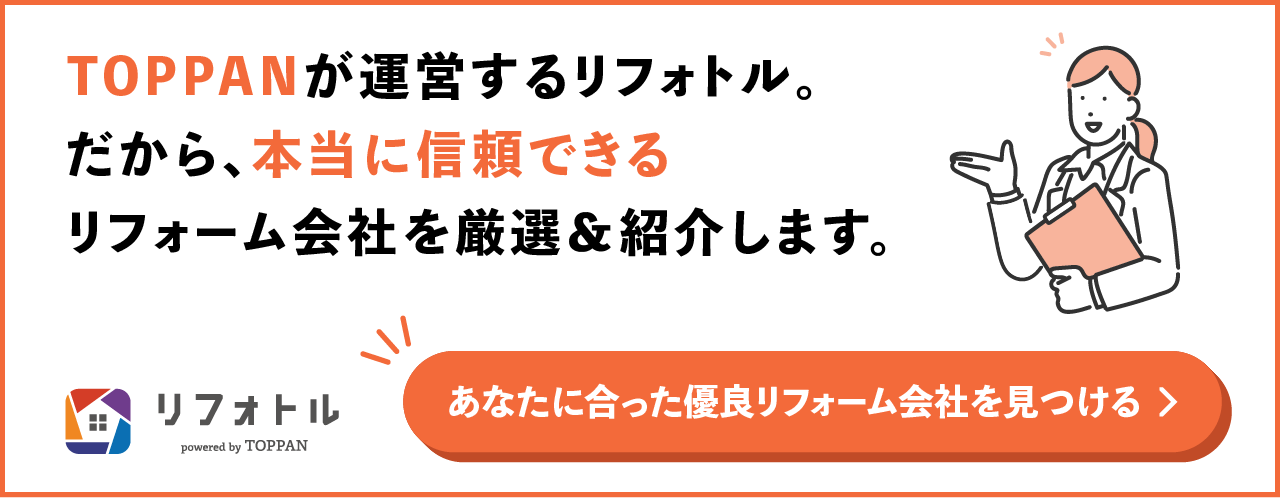
畳の上にフローリングを敷くメリット

畳をはがさずにフローリングを敷く方法には、工事をせずに雰囲気を変えられる手軽さや、掃除のしやすさなど、日常で感じる魅力がたくさんあります。
ここからは、次のメリットについて詳しく紹介します。
- 工事不要で手軽に洋室化できる
- 掃除が楽になる
- 畳の保護になる
工事不要で手軽に洋室化できる
最大のメリットは、手軽に和室の雰囲気を変えられる点です。
床材を張り替える工事を行わなくても、畳の上に敷くだけで洋室のような空間に仕上がります。作業は半日もあれば終わることが多く、家具を動かしながら自分で設置することも可能です。
また、DIYを楽しみながら部屋づくりをしたい方にとっても魅力的です。コストを抑えつつ印象を変えられるため、模様替え感覚で取り入れる方も増えています。
「大がかりなリフォームを行わずに気分転換をしたい」ときに、おすすめの方法です。
掃除が楽になる
フローリングを敷くと、掃除のしやすさが格段にアップします。
畳のようにホコリが目の間に入り込むことがなく、掃除機やロボット掃除機もスムーズに動かせます。べた付いた汚れや水分などもサッと拭き取れるため、部屋をきれいに保ちやすくなります。
特に、小さなお子様やペットのいる家庭では、掃除のしやすさは大きなメリットです。
畳に比べてメンテナンスの手間が少なく、日常の掃除が簡単になることで、家事のストレスを減らせます。
畳の保護になる
フローリング材を畳の上に敷けば、畳自体を摩耗や汚れから守れます。例えば、重い家具の脚によるへこみや変色、食べこぼしのシミなど、畳が直接受けてしまうダメージを軽減できるのも大きなメリットです。
ただし、湿気対策を怠ると逆効果になるおそれがあります。湿気がこもるとカビやダニの温床になり、畳そのものを傷める結果につながります。
畳を保護する目的で敷く場合は、防カビシートや調湿材を併用して、通気性を確保することが大切です。
畳の上にフローリングを敷くデメリットと注意点
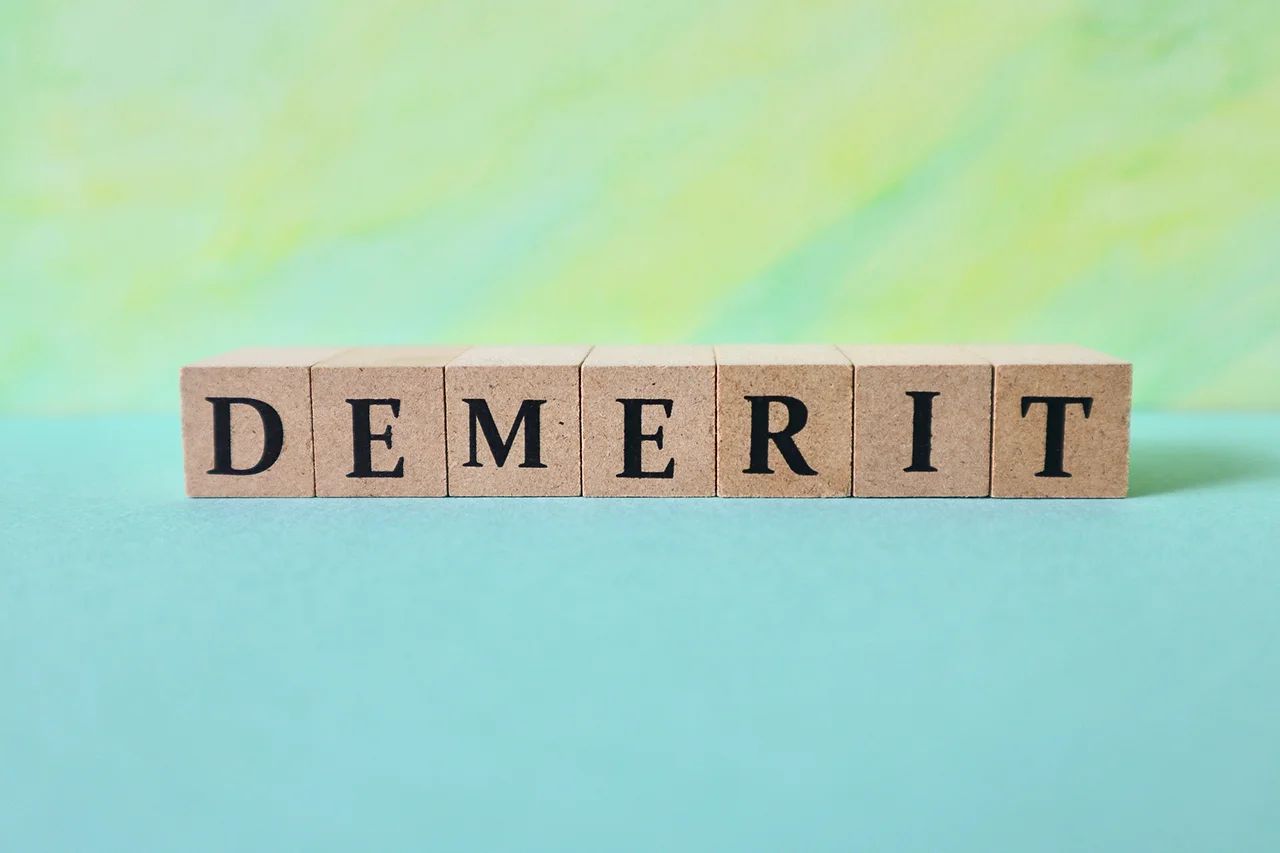
畳の上にフローリングを敷くのは、手軽で便利になる方法ですが、次のようなデメリットもあります。
- 畳にカビやダニが発生しやすくなる
- 段差ができる
- 見た目の調和が難しい
- 畳本来の機能が失われる
それぞれについて注意するポイントをまとめているので、事前に把握しておきましょう。
畳にカビやダニが発生しやすくなる
最も注意すべき点は、カビやダニの発生です。
畳の上にフローリングを敷くと、空気の通り道がなくなり、湿気がこもりやすくなります。特に梅雨時期や結露が発生しやすい部屋では、畳の内部で水分が溜まり続け、カビが繁殖しやすくなるため対策が必須です。
また、目に見えにくいダニが増えることで、アレルギーやかゆみなど健康被害を招くおそれもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、防カビシートや調湿材を活用して定期的にフローリングを外すなど、湿気対策を徹底しましょう。
段差ができる
畳の上にフローリング材を重ねると、その厚みの分だけ床に段差が生じます。また、ドアの開閉がしづらくなったり、隣の部屋との高さが合わなくなったりするケースもあります。
小さな段差でも、つまずきや転倒の原因になることがあるため注意が必要です。特に高齢の方や小さなお子様がいる家庭では、安全面に配慮した施工を行いましょう。薄型の製品を選んだり、敷く範囲を限定したりして、生活に支障が出ないよう工夫するのがポイントです。
見た目の調和が難しい
「洋室にしたいと思ってフローリングを敷いたのに、思ったほど印象が変わらず床だけ違和感がある…」といったケースもよくあります。違和感がでるのは、押し入れや床の間、障子やふすまなど、和室特有の要素がそのまま残っていることが原因です。
完全に洋風へ変えるよりも、和の雰囲気を活かしたコーディネートを意識すると、まとまりのある空間になります。たとえば、フローリングの木目や色味を落ち着いたトーンでそろえたり、障子の枠や建具を活かしたナチュラルモダンなスタイルに仕上げたりする方法もおすすめです。
フローリングを敷くだけで全体を変えようとせず、和の魅力を少し残せば、自然で心地よい空間に整えられます。
畳本来の機能が失われる
畳には、調湿性や断熱性など快適な室内環境を保つ役割があります。
フローリングを重ねることで畳本来の機能が働かなくなり、湿気がこもりやすくなったり、冬場に足元が冷えやすくなったりします。また、畳が持つ独特のやわらかさや香りを感じられなくなる点もデメリットです。
畳の機能を活かしながら見た目を変えたい場合は、部分的なリフォームやモダンなデザインの畳への交換など、別の方法を検討してみましょう。
畳のフローリング化が得意なリフォーム会社をご紹介!
カビ・ダニ・湿気を防ぐための対策

畳の上にフローリングを敷く際に最も注意したいのが、湿気対策です。カビやダニは目に見えにくく、気づいたときには畳の内部に広がっていることもあります。
ここでは、敷く前と敷いた後に行いたい具体的な対策を紹介します。
敷設前の畳の清掃・乾燥の徹底
作業前に、まずは畳の上をしっかり掃除しましょう。
掃除機で畳の目に詰まったホコリやダニの死骸、髪の毛や食べかすなどを吸い取り、必要があれば畳専用クリーナーを使って拭き掃除を行います。
湿気が気になる場合は、扇風機や除湿機、エアコンのドライ機能を使って乾燥を促すのも効果的です。
清掃・乾燥をきちんと行えば、フローリングを敷いた後のカビやダニ発生のリスクを大きく減らせます。作業日は、天気が良く湿度の低い日を選ぶのがおすすめです。
防虫・防カビシートや調湿材の活用
フローリングと畳の間に、畳用の防虫・防カビシートや調湿作用のある炭シートなどを挟むと、カビやダニを効果的に防げます。
特に、冬に窓際で結露が出やすい部屋や賃貸住宅で原状回復が求められる場合には、積極的に採用しましょう。湿気がこもるのを防ぎながら、畳を長くきれいに保てます。
シートを敷く際は、隙間ができないように重ねて配置し、端までしっかり覆うのがポイントです。ズレやたるみがあると、そこに湿気がたまりやすくなるため注意しましょう。また、フローリング材で床面全体を完全に密閉せず、四隅に少しだけ通気を確保しておくとより効果的です。
素材によっては防臭・抗菌効果もあるため、部屋の状態や使い勝手に合わせて選びましょう。
定期的な換気・掃除
数ヶ月使用した後にフローリングを外してみたところ、「畳に黒カビが生えていた!」というのは、よく耳にする話です。
フローリングを敷いたあとも、カビやダニを防ぐためには定期的なメンテナンスが必要です。月に一度程度はフローリングを部分的に外し、風を通すようにしましょう。さらに、掃除機でホコリを取り除いたり、乾いた布で拭き掃除を行ったりするのも効果的です。
小まめな換気と清掃を続ければ、畳とフローリングの両方を長持ちさせられます。
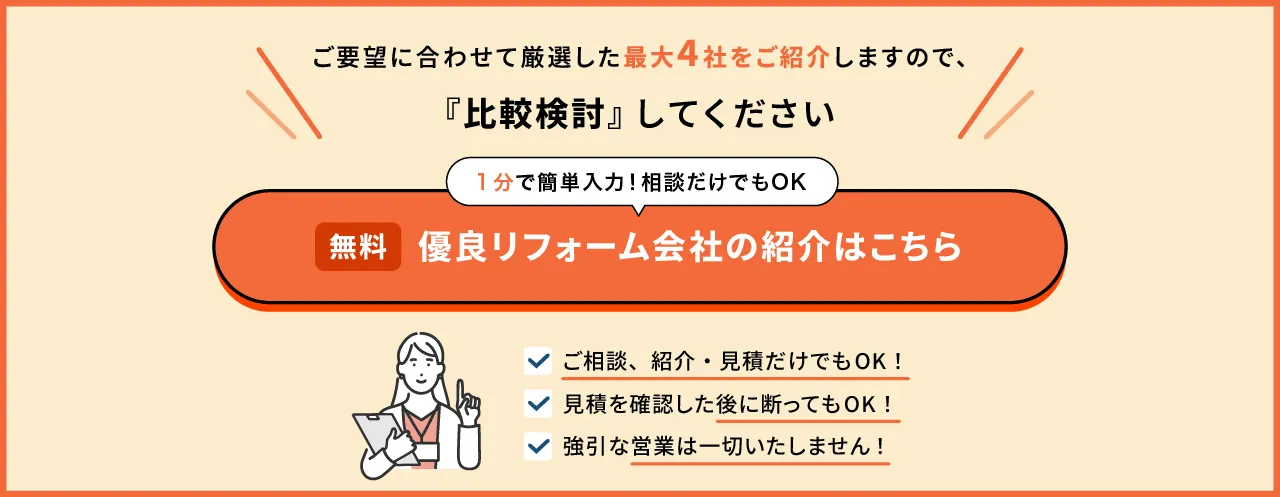
カビ・ダニが発生した場合の対処法
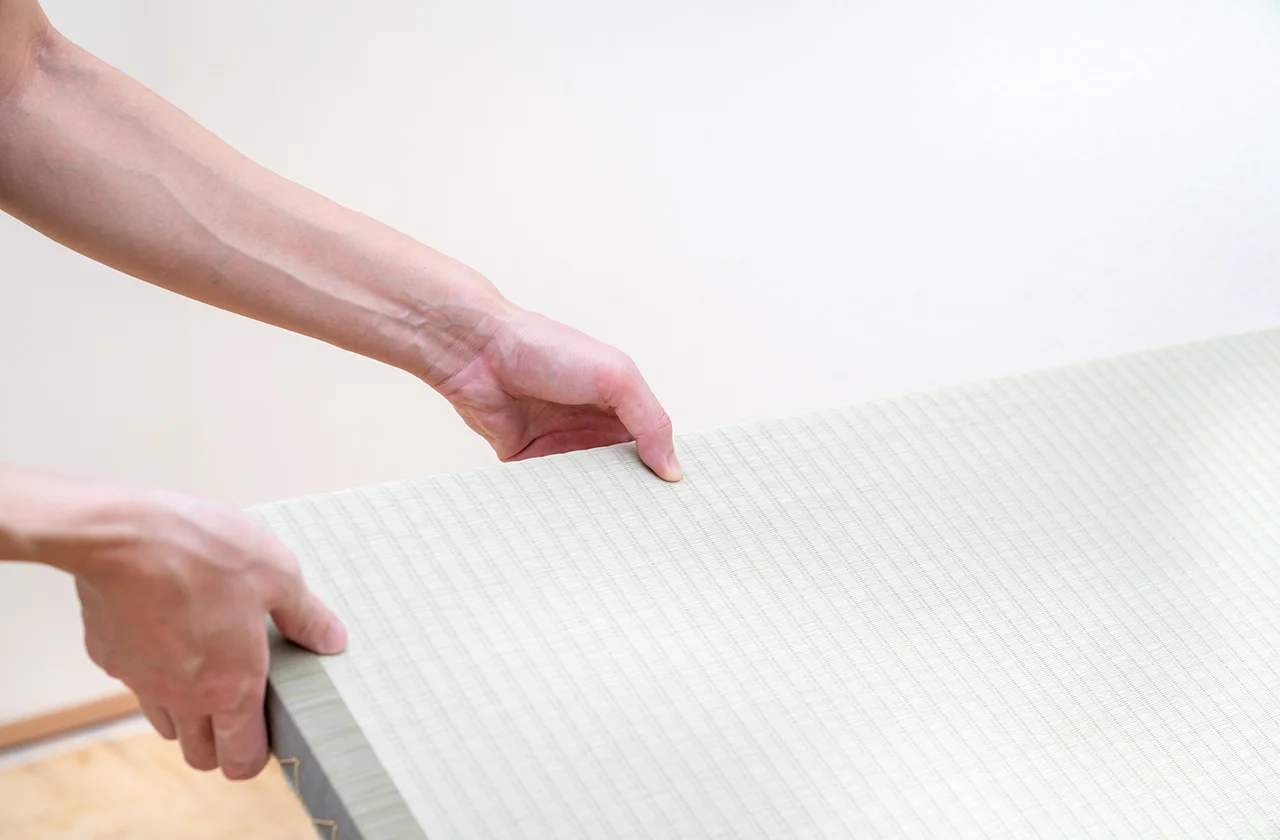
カビやダニが発生してしまった場合は、早めの対処が重要です。
カビが軽度なら、アルコールスプレーやカビ取り専用剤を使って拭き取ります。必ず風通しの良い状態で作業し、湿気を残さないようしっかり乾かしてください。
広範囲にカビが広がっている場合や、カビ臭が強いときは、専門業者への依頼を検討しましょう。畳の内部まで菌が入り込み、表面だけの掃除では完全に除去できない可能性があります。
また、ダニが発生したときは掃除機で吸い取ったあと、スチームアイロンを当てると効果的です。高温の蒸気がダニを死滅させ、卵の繁殖も防ぎます。
ただし、畳や下地が傷んでいる場合は、交換や張り替えが必要になることもあります。再発を防ぐためには、湿気の原因を取り除くことが必要です。除湿機の設置や通気の確保など、環境そのものを見直し、根本的な解決につなげましょう。
手間なくキレイ!畳リフォームをプロに依頼するメリットと費用相場

自分でフローリングを敷く方法は手軽ですが、長期間使うことを考えれば、専門業者に依頼する方がリスクも少なく安心です。
ここでは、プロに任せるメリットと費用の目安を紹介します。
畳リフォームをプロに依頼する場合のメリット
リフォーム会社に依頼すれば、畳の状態を見極めたうえで最適な施工を行ってもらえます。
カビや段差の発生リスクを最小限に抑え、見た目にも美しい仕上がりになります。床下の湿気や断熱性など、目に見えない部分まで考慮して施工してくれる点も大きなメリットです。
また、素材の選定から仕上げまで一貫して対応してくれるため、耐久性や快適性の面でも安心感があります。
DIYより初期費用はかかりますが、結果的にきれいで長持ちする床を実現できます。
リフォーム会社による畳リフォームの費用相場
畳をフローリングへリフォームする際は、使用する床材や工法によって費用が大きく変わります。
リフォーム会社に依頼する場合、畳を撤去して下地から新たに施工する「張り替え工法」が基本です。
畳を撤去してフローリングを張る工事は、畳の厚さ(55~60mm)に合わせて下地を組む必要があるため、既存のフローリングを張り替えるよりも費用が高くなる傾向があります。ただし、品質・耐久性・カビ対策の面でも安心で、長持ちする仕上がりになる点は大きな魅力といえます。
6畳程度の部屋で畳からフローリングに張り換えた場合、リフォーム費用の相場は次のとおりです。
| 床材の種類 | 6畳(約10㎡)あたりの費用相場 | 特徴 |
| 無垢フローリング | 15〜20万円 | ・天然木の風合い ・調湿効果や断熱性に優れる ・材料費が高価になりやすい |
| 複合フローリング | 12~17万円 | ・複数の層からなる ・耐傷性・耐水性・遮音性などに優れる ・デザインや機能が豊富で最も一般的 |
| クッションフロア (CF) | 5~10万円 | ・クッション性のある塩ビ素材 ・防水性に優れる ・デザインが豊富 ・価格が安く、取り入れやすい |
※上記の費用はあくまでも目安です。実際の金額は材料や下地の状況、仕上げ方により異なります。
なお、「重ね張り工法」(畳の上に合板などを重ねて施工する方法)は、費用を抑えられる一方で、畳内部に湿気がこもりカビや沈み込みの原因となることがあります。そのため施工品質の保証が難しく、リフォーム会社では断られるケースが多いのも実情です。
長く快適に使える床を目指すなら、張り替え工法を選ぶのがおすすめです。
畳のフローリング化が得意なリフォーム会社をご紹介!
畳をフローリング化するリフォームの流れ

ここでは、リフォーム会社に依頼して畳をフローリング化する場合の工事の流れを紹介します。
-
現地調査・見積もり
施工業者が現地を確認し、畳の状態や床下の湿気状況まで細かくチェックします。希望の施工内容や仕上げイメージ、見積もり価格を確認しましょう。
-
畳の撤去・下地処理
本格的なリフォームの場合、まず既存の畳を撤去し、床下の掃除や乾燥、防カビ・防湿対策など下地処理を実施します。床の高さ調整も、この工程で行います。
-
フローリング材の施工
フローリング材を丁寧に敷設していきます。部屋の形や段差に合わせてカットし、継ぎ目や壁際もきれいに仕上げます。
-
完成・チェック
施工後は全体をチェックし、問題がなければリフォーム完了です。工事期間は内容によりますが、一部屋で2〜3日程度が目安です。
住まいのリフォームでは、適正な価格と会社それぞれの特徴を知るためにも、「相見積もり」をして複数社を比較・検討するのがおすすめです。
リフォーム会社の紹介&比較サイト「リフォトル」なら、厳選した優良リフォーム会社を複数社ご紹介可能です。
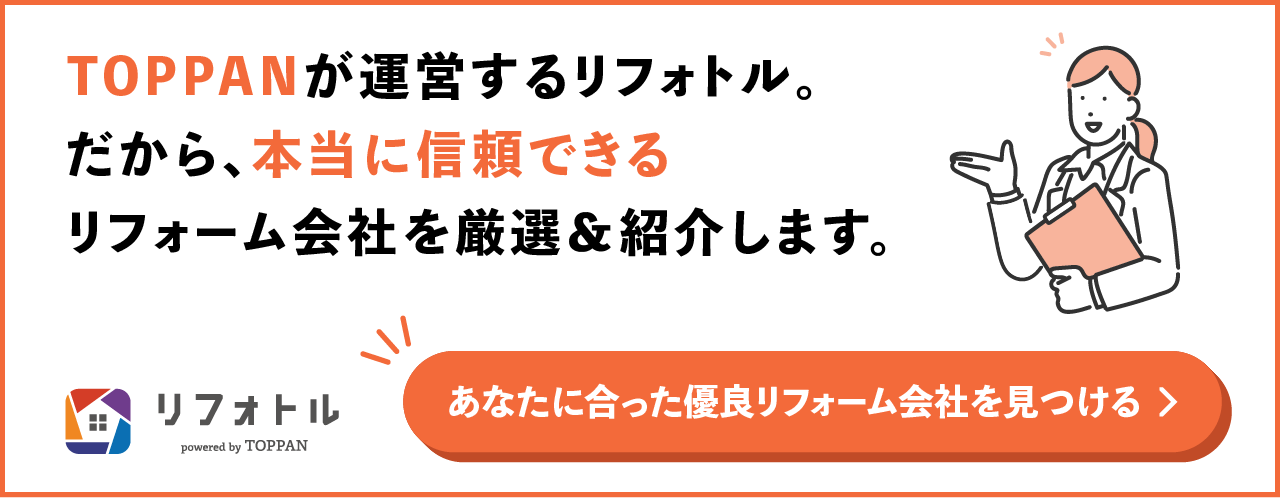
まとめ
畳の上にフローリングを敷く方法は、工事をせずに手軽に部屋の雰囲気を変えられる便利な手段です。
しかし、湿気や段差、見た目のバランスなど注意すべき点が多くあります。特にカビやダニの発生は健康にも影響するため、事前の準備と施工後のメンテナンスを欠かさないことが大切です。
短期間の模様替えや仮設的な用途であれば、置くだけタイプのフローリングでも十分に対応できます。しかし、畳の傷みやカビを気にせず長く快適に使いたい場合は、専門業者によるリフォームを検討してみましょう。
自分の暮らしに合ったリフォーム方法を見つけて、素敵な空間づくりを実現してくださいね。
TOPPAN(東証プライム上場)が運営する「リフォトル」では、国土交通省 登録団体に所属する優良リフォーム会社を無料で紹介しています。ぜひお気軽にお申し込みください。
国土交通省登録団体に所属する優良リフォーム会社をご紹介!
畳の上にフローリングを敷く際のよくある質問
畳の上に敷くなら何がいい?
短期間の模様替えならフロアタイルやフローリングマットで十分対応できますが、長く使う場合は耐久性のあるフローリング材やウッドカーペットがおすすめです。
畳の状態によっては、専門業者に相談して最適な方法を提案してもらうと安心です。
防カビシートを畳の上に敷いたらダメ?
通常は畳の下に敷く防カビシートですが、フローリングを重ねる際は上に敷いてもOKです。
ただし、畳の状態や部屋の湿度によっては、シートが逆効果になることもあります。不安がある場合は、施工実績が豊富なプロに相談してみましょう。
畳の上にフローリングを敷いても元に戻せる?
接着剤や釘を使わなければ、原状回復は可能です。
ただし、長期間使用すると畳が沈んだり変色したりする場合があります。きれいな状態で戻したい場合や、畳の傷みが心配なときは、専門業者に点検を依頼して判断を仰ぐと良いでしょう。
信頼できるリフォーム会社をお探しの方へ
国土交通省 登録団体所属の信頼できるリフォーム会社の中から、
あなたの希望に合う複数社を無料でご紹介します。
国土交通省 登録団体所属
信頼できる会社を最大4社ご紹介します!
信頼できるリフォーム会社をお探しの方へ
国土交通省 登録団体所属の信頼できるリフォーム会社の中から、
あなたの希望に合う複数社を無料でご紹介します。
国土交通省 登録団体所属
信頼できる会社を最大4社ご紹介します!

