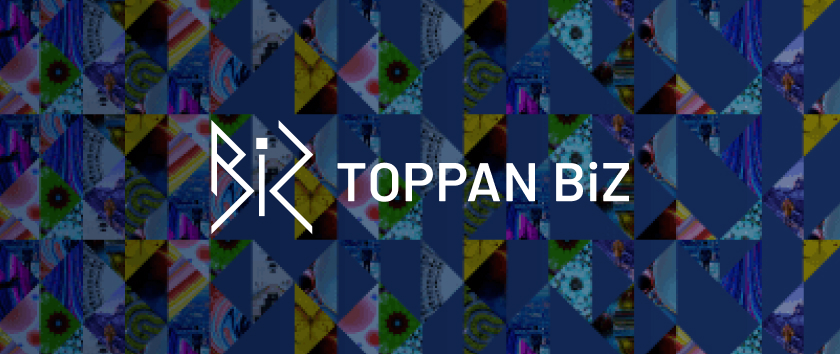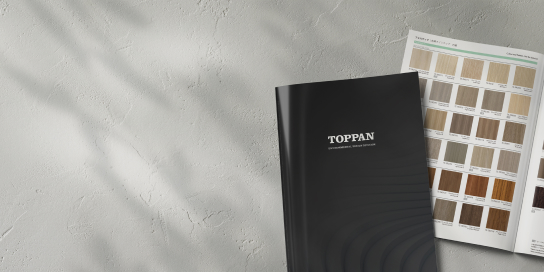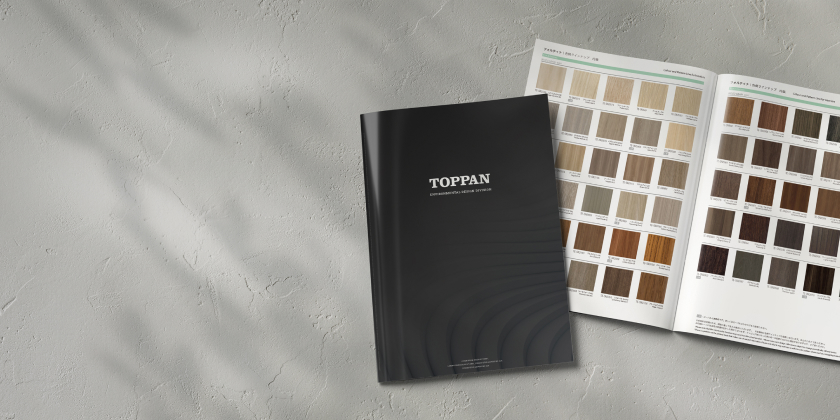和紙が拓く、新しい循環のかたち。マテリアルトライアル2

日本で昔から親しまれてきた和紙。近年ではファッションやインテリアをはじめとするさまざまな分野で、その活用方法や独自の質感・特性が改めて注目されています。
C-lab. が推進する、様々なジャンルのデザイナーと建材の新たな可能性を探る実験的プロジェクトである「マテリアルトライアル」。今回、グラフィックデザイナーの田中義久氏との共創で制作した和紙素材が、ニューバランスとのプロジェクトで採用されました。「アップサイクル」をテーマにした本プロジェクトにて、和紙素材がシューズの一部や空間演出として展開。一般的に想像する、和紙のイメージをアップデートするような実験や展示が行われました。
マテリアルトライアルでの取り組みをはじめに、ニューバランスでのプロジェクトの背景、創作プロセス、そして未来への展望を田中氏にお聞きしました。

ー 今回の展示の肝である、和紙。魅力を感じたきっかけは、2018年の竹尾ペーパーショウでアートディレクションとして関わった経緯からと伺いました。
そうですね。それまでも紙媒体を中心としたデザインを行なってきたので、以前から紙素材について関心があったのですが、特に日本は紙の種類が豊富で、コンセプトに合わせて様々な手法を試せる印刷物のクオリティを感じていました。一方で、紙媒体の総生産量は、やはりインターネット普及以降に年々減っていて。情報を定着させるメディアとしても、紙媒体よりデジタル媒体が主流になったこともあり、改めて情報を紙から切り離した時の「紙そのもののあり方」を考えるタイミングでした。大きなきっかけとなったのは、竹尾ペーパーショウで和紙をテーマとしたリサーチを始めたことですね。そこで見えてきたのは、工芸的なイメージが強く、現代的なアプローチが試されていないこと。でも色々とリサーチを重ねると、独自の機能性や物質性も明確に見えてきて、和紙なら紙の有意性を担保できると思ったんです。それを機に、ペーパーショウ以降も自主的に和紙についてリサーチを進めるようになりました。
ー たしかに、和紙は古典的なイメージがある一方で、素材として見ると意外と耐久性が強いことから他の紙に比べて長く使える方法がさまざまにありそうですね。本プロジェクトでは、和紙と靴の端材を掛け合わせた素材開発を試みていますが、どのようなプロセスで進めていったのでしょうか?
2020年からTOKYO DESIGN STUDIO New Balanceと協働し、靴の生産方法における新しいやり方やデザインを模索しています。サステナブルについても世の中の関心が強まってきた時代背景も相まって、おのずと和紙と靴の端材の組み合わせを試すようになりました。しかし、靴は予想以上に強度が求められるプロダクトでしたので、すぐさま短期間で紙で靴を作るということは構造的に難しく、本展に至るまでリサーチと実験含めたプロジェクトを2回行いました。

ー これまでの展示について教えてください。
第一回目は、実際に靴の生産工程で出てくるスエードや革など様々な端材をまずは繊維状に戻すところから始めました。その後、和紙と組み合わせて、また一枚の和紙にしてから既存の靴の型に当てはめて組み上げたものを展示して。靴だけではなく、シューズボックスやシューレースなど関連した部品の制作も同じように試みましたね。シューズボックスは、また靴とは違い、梱包としての耐久性が問われるものだったので、オリジナルのダンボールと組み合わた3層構造に仕上げ、表面の一枚に和紙を採用しました。将来的にシューズが完成したあかつきには、シューズボックスも実際に使えるクオリティにしています。第二回目は、靴は作らず、ユーザーが靴を使うサイクルに焦点を当てました。どうしても靴って履き潰したら捨ててしまいますよね。でも本来は定期的な補修やクリーニングさえ施せば、より長く使えるようになる。そこで、店舗にニューバランスで購入した靴を持ってくれば、クリーニングできるサービスボックスを設置しました。最終的に、綺麗になった靴を第一回目で作ったシューズボックスに入れてお渡しするような仕組みにしました。

ー 靴を開発するだけではなく、ユーザーの意識も一緒にアップデートしていくと。
そうですね。このプロジェクトで、最初から達成したかった目標は、どんなに型を変えても作るたびに出てくる端材すべてを和紙が請け負えるようになること。例えば、靴が1足作られるごとに、その端材で出来た靴が和紙との組み合わせで生まれるといったような新たな生産方法を考えていきたいです。大量生産・消費はそう簡単に止められないので、別の角度からエコロジーサイクルを持ち込めるように、今後もプロジェクトでリサーチを進めていきます。
ー それらの実験を経て、直近の第三回目の展示ではどのようなアプローチを試みたのでしょうか?
今回は、いままでの素材開発を活かして、一から考えたシューズデザインをもとに、新たな一足を完成させました。一般的に靴は、何十種類の生地の組み合わせで出来るパターンで出来ていますが、今回は紙の特性を活かすために1枚のパターンの中で作りました。踵の部分を折って強度を出したり、紙だからこそできるパターンや構造に試みることで、デザインからも和紙を使う意味を表現できたと思います。



ー TOPPANのC-labとの取り組みについて教えてください。
TOPPANのC-labとは、印刷物よりも、建材としての和紙の可能性を一緒に考えています。今回は、主にファサードと店内什器の制作に向けて取り組みました。まず、和紙の選定から始めていき、和紙以外にも土を混ぜたり、屋外での仕様として撥水性を保つためのコーティングの技術を考えていったり。店内什器にも同じ素材で、一般的に椅子の座面に使われるペーパーコードを採用しました。実際、強度だけ考えれば、編み込む回数を増やせば増やすほど、布と変わらないくらいの強度が保てるんですよね。でも今回のプロジェクトでは、そこを紙の軽さや見た目、そして触った時の表情を活かす形で、紙でしか見えないものを残しつつ、機能性も上げていくバランスを模索しました。例えば、構造としてはネットと同じですが、風によって軽やかな揺れ動きや柔らかな印象を表現できることは紙独自の魅力だと思います。こうした見え方のバランスは、最終的に出来てから気付かされることも多いです。

ー 今回の展示を拝見して、いい意味で和紙とは一見予想が付かないアウトプットで驚きました。
ファサードに関しては、そもそも紙が耐えるなんて思わないじゃないですか。展示期間中に4回ほど台風に遭遇していますが、この1ヶ月間をファサードとしてあり続けることは重要でした。もちろん今まで実験は積み重ねてきているので、ある程度どのような結果になるか予想はしていましたが、初めて見る人からするとまさか紙が外に吊るしてあるとは思わないだろうと。そこから意識転換にも繋がるといいなと思いました。これまで様々な企業と取り組んできましたが、なかなかマテリアル開発まで出来ても、実装として採用されないことが多くて。理由としては、それらを使いこなす手段がわからないという課題があります。機能性だけではなく、機能を豊かに、感受性に訴えかけられるものとして見せるにはどうするか。そこを一気通貫で開発者が考えるのは難しいと思いますし、だからこそデザインの意味が発揮されるのだと思います。

ー 素材をよくわかっているからこそ、客観的にその特性を理解して応用転換できるかというと難しいですよね。
マテリアルの意味を踏まえつつ、どのように可能性を伝えていくか。デザイナーも普段の仕事では、すでに存在しているものを意識しながら形にするので、今回のように一から取り組んで新しいものを開発することは滅多になく、そうした意識も希薄だと思います。だからこそ両者が協力し合う意義と可能性を今回のプロジェクトでは感じました。
ー 今後は、開発した素材をどのように展開していきたいですか?
テント幕のような簡易的に持ち運べる仮設建築を作りたいです。軽いので、誰でも持ち運べて、広げられるものを考えています。今回の展示のように数週間〜数ヶ月、屋外で使って実験したいですし、新しい和紙の魅力を伝えられると嬉しいです。自分だけで和紙についてリサーチを続ける活動と違って、さまざまなコラボレーションによって、みんなで可能性を引き出せる近道が作れるように感じて。さらに取り組みを見た方々が、新たな想像を膨らませて、想像の輪が広がっていってほしいです。
素材のもつ特性を活かす形で、現代的なアプローチを試みた本プロジェクト。「素材そのものの価値」とは一体どのようなものなのか。「マテリアルトライアル」では、日常に潜む素材の力を引き出し、未来の生活やものづくりに広がるインスピレーションを提供していきます。
インタビュアー: 倉田佳子
フォトグラファー: 小林茂太